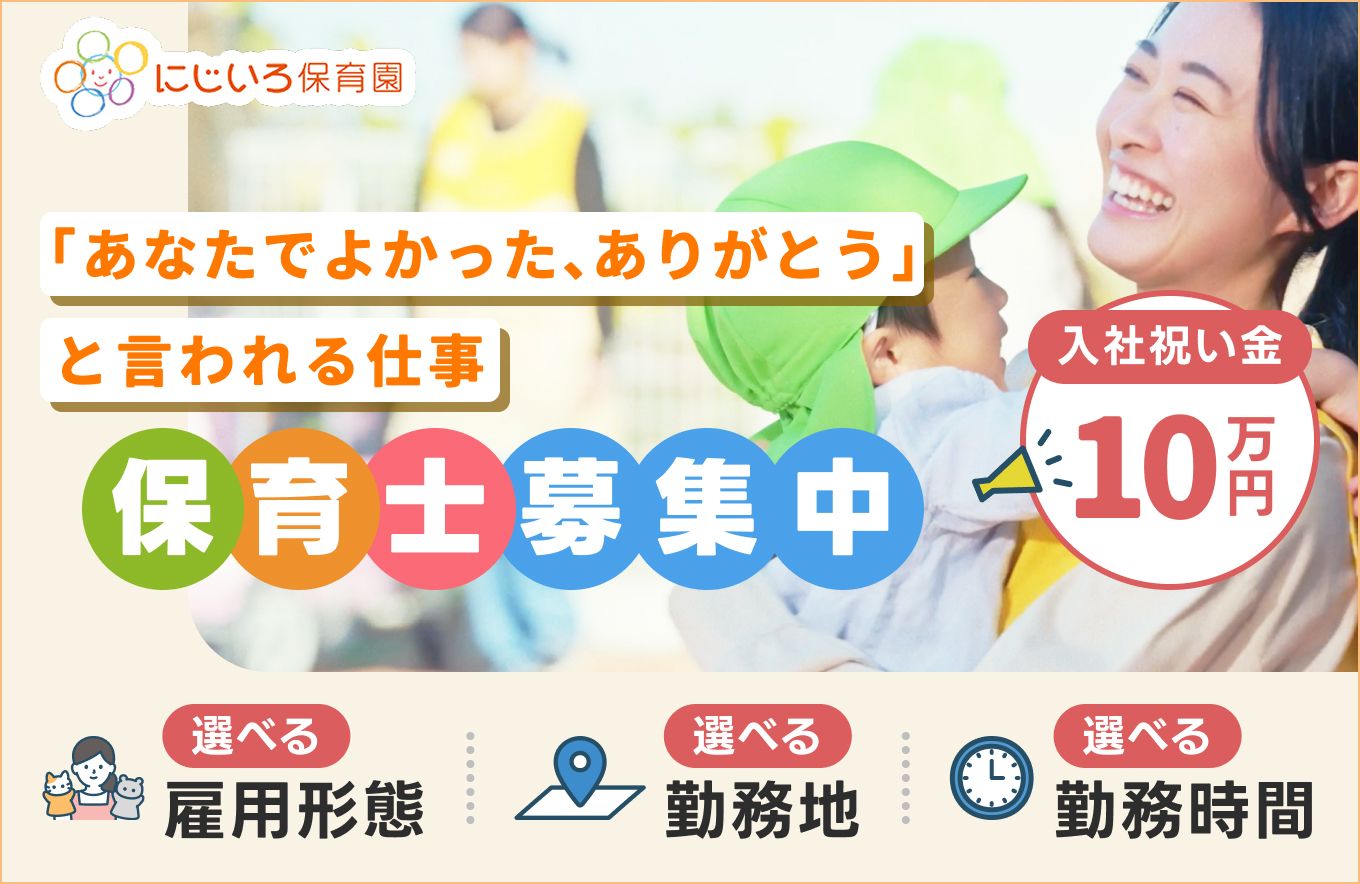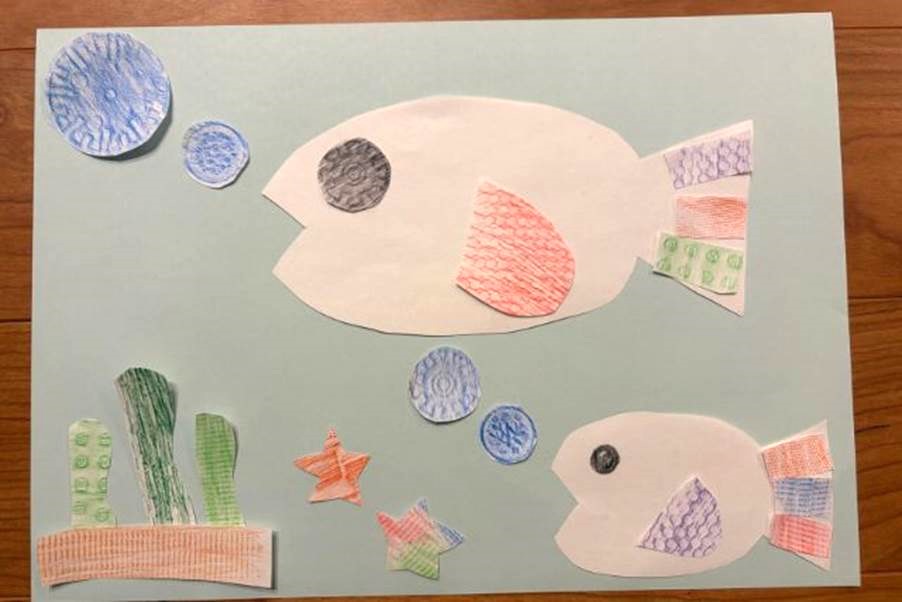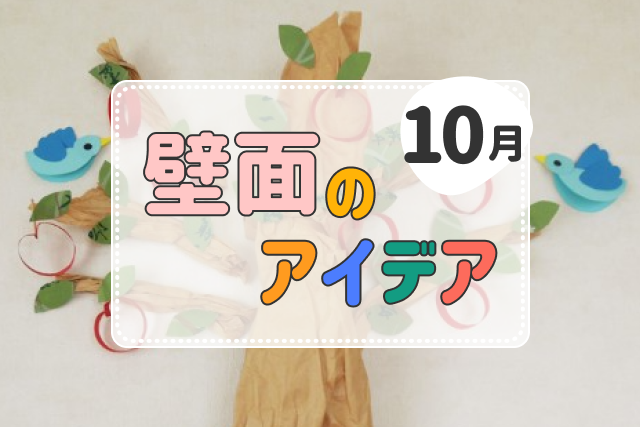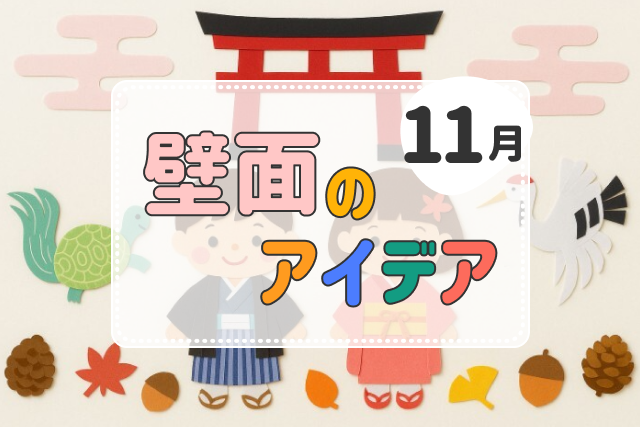2025.11.26
【保育園の1月遊び】ねらいが立てやすい!季節を楽しむ活動アイデア集
新しい年の始まりとともに、気持ちを新たに園生活がスタートする1月。年末年始のお休みが明けて、先生や友達と久しぶりに顔を合わせた子どもたちは元気いっぱい!寒さが増すこの季節は、外遊びと室内遊びの臨機応変な切り替えも必要になってきます。この記事では、1月ならではの遊びアイデアと、活動の“ねらい”を立てるためのヒントをご紹介します。
1月遊び「ねらい」の立て方のヒント

1月は、お正月ならではの遊びなどをきっかけに、体を動かす喜びやルールのある遊びの楽しみ方に親しむチャンスです。
乳児(0~2歳児)には、初めて触るおもちゃや道具の感触を楽しんだり、「投げる」などの動作を繰り返したりすることを通して、自分なりに遊び方が上達していく楽しさを感じることを目指しましょう。
幼児(3~5歳児)には、伝承遊びや正月ならではの文化に親しむ機会を通して、言葉・動き・人とのやりとりを広げる経験を効果的に増やしていきます。
外遊びと室内遊びをバランス良く取り入れながら、集団での遊びを積極的に展開していきましょう。
1月のおすすめ遊びアイデア
1月におすすめの遊びを、対象年齢の目安や年齢や成長に沿った遊び方、「遊びのねらい」などとともにご紹介します。
ふわふわ羽根つきごっこ

風船を使って楽しむ、やさしい羽根つき遊びです。羽子板を紙皿や牛乳パックなどで作り、風船をぽんぽんと打ち合うだけで、子どもは夢中になって体を動かします。風船の動きがゆっくりなため、空間認知やタイミングをつかむ練習にもぴったりです。
紙皿などで作った羽子板にはストローや割りばしなどで持ち手を付けたり、好きな絵を描いたりするなど、製作活動と組み合わせるのもおすすめです。
伝統的な羽根つきのようにお正月遊びとしても楽しめますが、季節を問わず屋内外で安全に行えるのが魅力です。
対象年齢
2~5歳児
基本のルール
- 向かい合って、風船を床に落とさないように交互に打ち合う
- 相手が風船を落としたり、返せなかったりしたら1点獲得
- 「5点」「10点」など、最初に決めた点数を先に取った方が勝ち
※地面に線を引いて自分のエリアと相手のエリアを決め、「自分のエリアから出てはいけない」「打った風船は相手のエリアに入れる」というルールを追加すると、より難易度が上がり楽しめる
遊び方のバリエーション
-
ロープで羽根つき(2~3歳児向け)
ロープを子どもよりも少し高い位置に張り、ひもで風船をぶら下げます。子どもは紙皿や牛乳パックなどで作った羽子板で、風船をぽんぽんと打ちます。勝敗にこだわることなく、「自分でタイミングを見はからって打つ」という感覚を自然に学ぶことができます。
風船だけでなく、小さく切ったスポンジや束ねた毛糸などの柔らかい異素材をぶら下げると、素材ごとの動きの違いを感じ取る楽しさが広がります。子どもの発達に合わせて、ロープの高さや素材を調整しましょう。
- 的あて羽子板(4~5歳児向け)
枠の中に点数を描いた的(まと)を段ボールなどで作って壁に貼り、風船を打って当てる遊びです。
個人戦では1人ずつ順番に打って点数を競い、チーム戦ではグループごとに合計得点を競います。「合計点数が一番多いチームが勝ち」というルールのほか、「合計点数がちょうど〇点になるようにする」というルールに変えると、ぐっと難易度が上がり、数字への関心を引き出すこともできます。「当たった場所を判定する係」を決め、子どもたちが交代で行うのも良いでしょう。
また、「ペアを作り、1人が打った風船を、もう1人がうちわであおいで狙った的に当てる」というルールで行うと協力し合う楽しさを味わうことができ、友達と力を合わせて目標を目指す達成感が得られます。
この遊びのねらい
風船を目で追い、腕を使って打つ一連の動きの中で、目と手の協応動作や反応する力を育てる遊びです。風船の動きを予測して打つことで、空間を捉える力やタイミングを判断する力が養われます。また、友達と向かい合って打ち合ったり、チームで点数を競ったりすることで、協力する喜びや相手を意識して動く力が身に付きます。うまく打てなかったときも「もう一回!」と気持ちを切り替え、再び挑戦する経験を通して、意欲や自信を育てることにつながります。
くっつきボール遊び

養生テープの粘着面を的にして、柔らかくて軽いカラーボールをくっつけて楽しむシンプルで楽しい遊びです。養生テープは遊具と遊具などの間にピンと張って的にします。ボールを、養生テープに向かって投げると「ペタッ」とくっつく様子が面白く、また簡単にはがせるので、何度でも繰り返し遊ぶことができます。狙って投げる動作はもちろん、「どんな角度や強さで投げたら良いか」を考える力や手先をコントロールする力が育ちます。
対象年齢
2~5歳児
基本のルール
- 養生テープを遊具などの間に、粘着面が前に向くように張って、的を作る
- 地面に線を引き、その線を越えない位置からボールを投げる
※何個くっつけられたかを数えたり、ボールの大きさを変えて挑戦したりしても楽しめる
※ジャングルジムの上の段から下の段まで粘着テープの的を作り、ボールがくっついた段によって点数を付けて競う遊び方もできる
遊び方のバリエーション
動く的遊び(3~5歳児向け)養生テープを貼り付けた段ボールや厚紙などを、保育士が持って的を動かします。子どもは動く的に向かってボールを投げ、くっつけられたら成功!
「走る的」「ジャンプする的」「くるくる回る的」など、的の動きを変えることで難易度が変わって楽しめます。
子どもは的の動きを目で追いながらタイミングを見計らって投げるため、集中力や反応する力が育ちます。
- カラー的あてチャレンジ(4~5歳児向け)
段ボールなどで赤・青・黄などの色別の的を作り、それぞれに養生テープを貼ります。的の前にボールをたくさん入れたカゴを置き、子どもはスタートの合図と同時に同じ色のボールを探し、同じ色の的にくっつけていきます。制限時間内に何個くっつけられるか挑戦したり、リレー形式でタイム
を計ったりしても楽しめます。
また、「黄色に3個、赤に2個」というように保育士がお題を出した遊び方では、数への興味や色を認識した思考力を引き出すこともできます。
チーム戦の場合は、赤チームは赤いボールを赤の的へ、青チームは青の的へくっつけるというルールで行うと、「自分のチームのボールを探す係」「受け取ってくっつける係」などの役割が生まれてくることもあり、遊びながら協力する楽しさが育てられます。「次は逆の係でやろうか」など、保育士が状況を見て声かけを行いましょう。
この遊びのねらい
くっついたときの達成感と、はがして何度も繰り返せるシンプルな楽しさが味わえるので、低年齢にもおすすめの遊びです。
狙う・投げるという一連の動きを通して、腕や手の動かし方をコントロールする力を育てます。ボールをどこにどう投げたらうまくくっつくかを考える中で、空間を捉える力や判断力も自然に養われます。
動く的やチーム戦で友達と一緒に取り組むことで、協力する喜びや競い合う面白さを経験し、意欲や自信を深めることができます。投げ方のコツを教え合ったり、オリジナルの的を作ったり、さまざまな展開ができる遊びです。
サイコロけんけんぱ

「けんけんぱ」とサイコロを組み合わせた、楽しい運動遊びです。サイコロを振って出た目の数に合わせて、「けん(片足)」と「ぱ(両足)」を組み合わせながら進みます。普通の「けんぱ、けんぱ、けんけんぱ」のリズムではなく、サイコロの数字に合わせて進まなくてはいけないので、リズムの取り方が難しく、集中力と判断力が育ちます。バランス感覚を養うのにもぴったりで、「次は何が出るかな?」と笑顔が広がる遊びです。
対象年齢
4~5歳児
基本のルール
- 地面に「けん(片足)」「ぱ(両足)」の円を描き、けんけんぱのコースを作る。サイコロを振って出た目の数だけ、「けん」「ぱ」を組み合わせて進む
- ゴールまで進めたら成功
- 途中でバランスを崩したり、コースから外れたりしたらスタート地点に戻る
遊び方のバリエーション
ミッションつきサイコロ(4~5歳児向け)各面に「ミッション」を書いたサイコロを準備します。「ミッション」には、「はくしゅ」(拍手しながら進む)、「どうぶつ」(止まったら動物ポーズ)、「うしろむき」(後ろ向きで進む)など、動作を加えるミッションを入れると難易度がアップして楽しめます。サイコロを振る役目も交代で子どもが行うと、「次は何が出るかな?」「アレが出てほしい!」と、みんなでワクワクしながらサイコロの出目を見守るので盛り上がります。
動作を加えたけんけんぱで、子どもがうまくバランスがとれない場合は、「ゆっくりでいいよ」「1つずつ進もう」などと保育士が声をかけましょう。友達のやり方を見てまねをしたり、コツを教えてもらったりすることで、体の動かし方が少しずつ身に付きます。
- コースけんけんぱ(4~5歳児向け)
けんけんぱのコースの途中に、特別なスポットを作ります。「なわとびゾーン」「ジャンプゾーン」「回転ゾーン」などを設定し、そのスポットでは必ず止まり、指定された動作を行います。止まったらもう一度サイコロを振り、「3が出たらジャンプ3回」「5が出たらなわとび5回」など、サイコロの数と動作を組み合わせると、遊びの中に自然と数の学びが生まれます。
友達とコースを延長して作ったり、チームでリレー形式にしたりすると、協力しながら楽しめる運動遊びにも発展できます。
この遊びのねらい
ベースとなる「けんけんぱ」は、「けん(片足)」と「ぱ(両足)」を組み合わせた動きの中で、バランス感覚や脚の筋力を養う遊びです。サイコロの出目に合わせてリズムを変えたり、ミッションに沿って体を動かしたりすることで、瞬発力や判断力が身に付きます。
また、子どもたちでグループを作ってサイコロのミッションを何にするか相談したり、協力してコースを作ったりする中で、発想力や協同性を高めていくことができます。
ポイントコマ回し

点数が描かれたシートの上でコマを回し、止まった場所の点数を競う遊びです。昔ながらのコマ回しに「得点獲得」の要素を加えることで、回す楽しさとゲーム性の両方が味わえます。手で回すコマ、ひもを使って回すコマどちらでも楽しむことができ、室内で安全に行えます。力の入れ具合や、回し方などを繰り返し試してみることで、指先の器用さや集中力を育てることにもつながります。
対象年齢
4~5歳児
基本のルール
- 画用紙などに円を描き、中心から外に向かって「10点」「20点」「30点」などの点数ゾーンを作る
- 子どもは順番にコマを回し、止まった位置の点数を記録する。複数回行い、合計点で勝負しても良い
- コマがシートからはみ出した場合は「0点」とする
- 点数を記録したら点数ゾーンからコマを取り除き、次にコマを回す子どもと交代する
※2人同時にコマを回し、止まった位置の点数を競うルールにしても楽しめる
遊び方のバリエーション
- 目隠しコマ回し(3~5歳児向け)
目をつぶったり、柔らかい布(タオルや手ぬぐいなど)で目隠しをしたりして行うコマ回しです。
子どもが定位置でコマを構えたら、保育士が目隠しをします。「スタート!」の合図で目隠しをしたままコマを回します。コマが止まったら目隠しを取り、何点のゾーンに止まったかを確認します。見えない状態で回すことで、感覚を頼りに力加減を調整する経験ができます。「どこに止まったかな?」と想像したり、「今度はもう少し勢い良く回してみよう」と試したりする中で、試行錯誤しながら目標に近づこうとする力が育ちます。
- コマ迷路(4~5歳児向け)
段ボールや厚紙の上に割りばしやストローなどを貼り付け、簡単なコースの台を作ります。スタートからコマを回し、台を傾けながら「どこまで進めるか」「ゴールできるか」を楽しむ遊びです。長く立っていられるようにコマを回す必要があること、コマの動きを見ながら慎重に台を傾ける必要があることから難易度は高めです。最初はまっすぐ進む短いコースから始め、少しずつカーブや障害物を増やすと、少しずつクリアする達成感が味わえます。「ここを通れたら10点」「ここを曲がれたら30点」など、通過点でのポイント要素を加えると、より集中して楽しむことができます。
この遊びのねらい
指先を使ってコマを回すことで、手先の器用さや集中力を育てる遊びです。コマの動きを見ながら、力加減やタイミングを調整する経験を重ねる中で、繊細なコントロール力も磨かれます。ゲームの勝敗だけでなく、粘り強く取り組むことの大切さが実感できます。
家庭でも簡単にできる室内遊びなので、園からのおたよりで子どもたちがコマ遊びに親しんでいる様子を伝え、家族で一緒に楽しめる遊びとして紹介するのもおすすめです。
1月の遊びを充実させるヒント

1月の遊びを充実させ、子どもたちの満足感や成長を促す工夫をご紹介します。
新年の空気感を楽しみ、園生活のペースを整える
お正月ならではの遊びなど、日本の伝承文化に触れる機会が増える1月。初めて経験する子も多いかもしれませんが、好奇心にあふれた子どもたちは、保育士が遊び方を楽しそうに伝えることで自然と関心が深まっていきます。年長児がやり方を教えてあげたり、一緒に遊ぶところから始めたりするのも効果的です。
1月は「年末年始に生活リズムが崩れた」という子どもが少なくない時期でもあります。日常の流れに戻るまでは無理に活動を増やさず、子どもの「やってみたい」という気持ちに寄り添いながら、それぞれのペースを見守りましょう。
1月の遊びをより豊かにする+αのアイデア
ひと工夫することで、子どもの「楽しかった!」や「またやりたい!」を引き出しましょう。
- 羽根つきやコマ回しなどで遊ぶ前に、簡単に由来や昔の遊び方をイラストなども使って紹介し、伝統文化への興味を自然に育てる。
- その年の干支の動きをまねして「〇〇さんになって走ろう!」などのゲームを展開。干支の知識とともに、体の使い方と想像力の両方を育てる。
- 園庭や公園で「木の枝はどうなっている?」「木の葉の色は?」など、寒さの中で見つけられる自然の変化に気づきながら遊ぶ。
まとめ
1月は新しい年の始まりにふさわしく、遊びの中でもさまざまなことに挑戦できる月です。子どものペースを大切にしながら、伝承遊びや冬の自然に触れる活動を通して、子どもたちの好奇心や伝統への関心を育てていきたいですね。