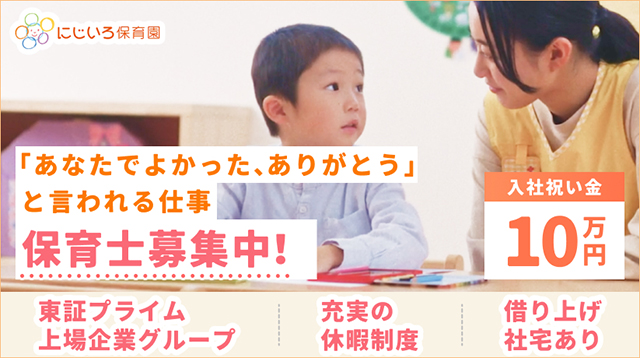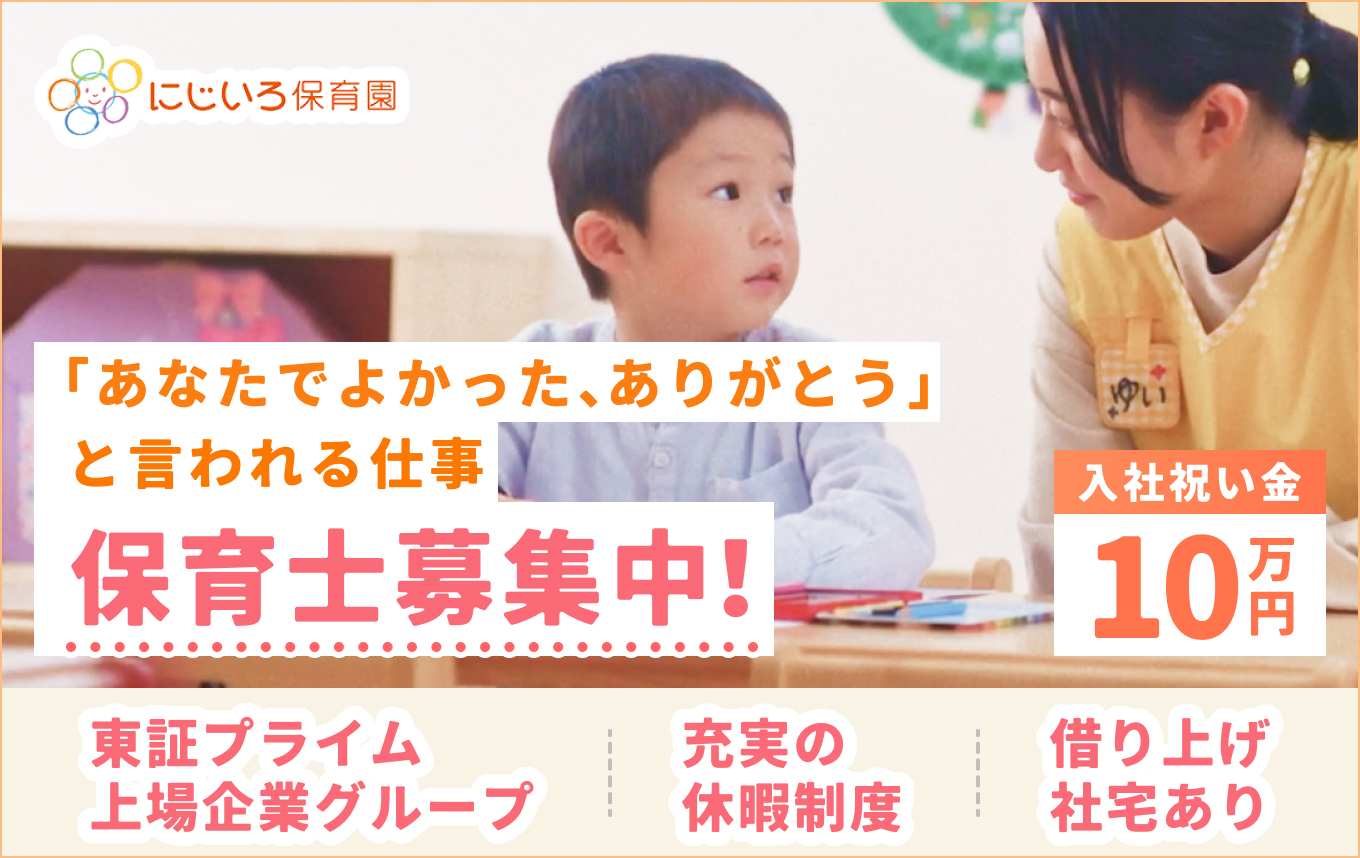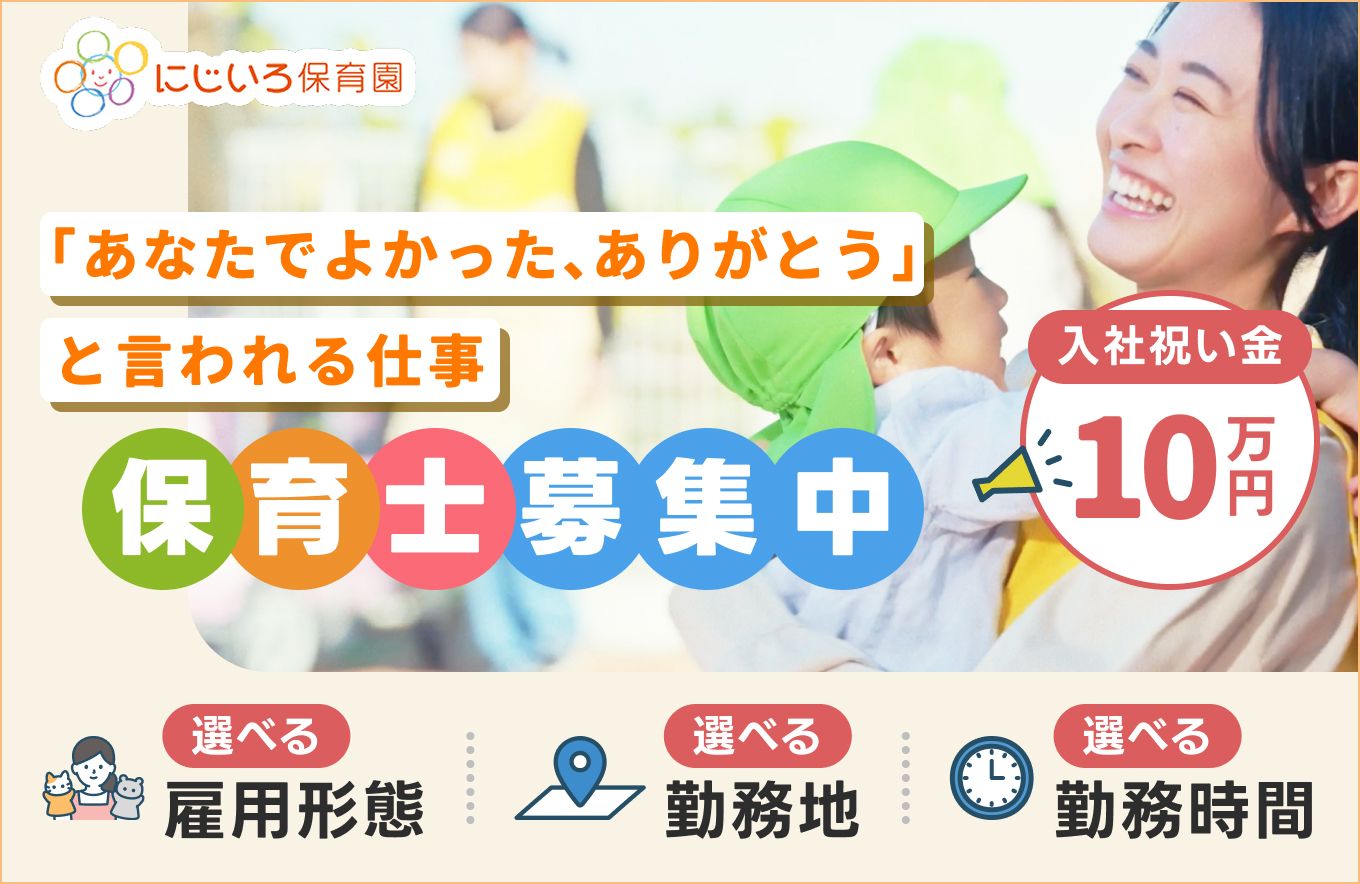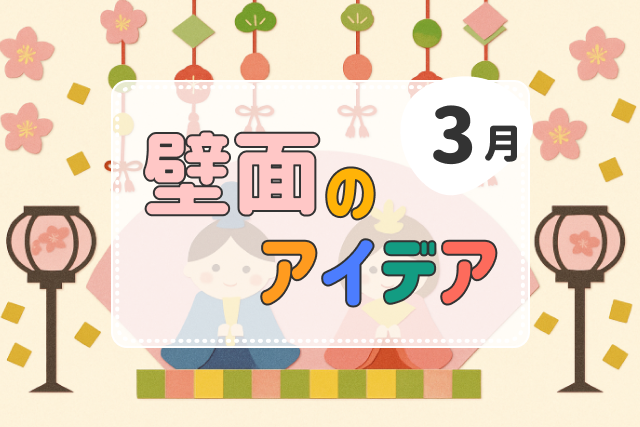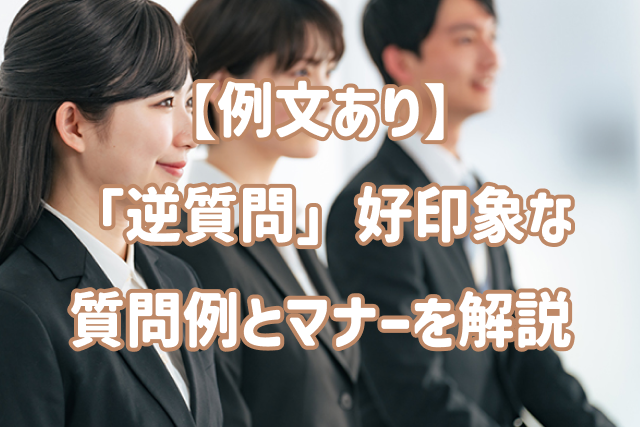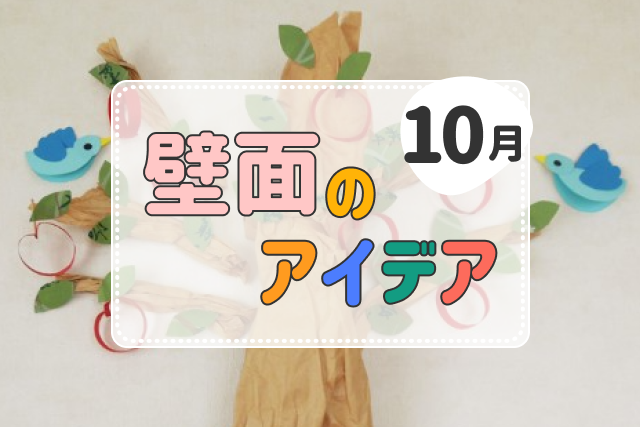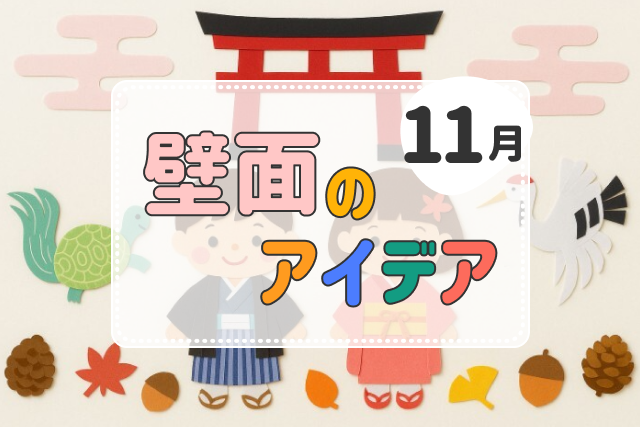2025.10.24
保育園だより12月号|おたより文例集
12月は年末に向かって、園も保護者たちも慌ただしい季節。伝えなくてはいけないことがしっかり伝わるよう、メリハリをつけたおたよりづくりを心がけましょう。この記事では、12月に園からご家庭へお届けする「おたより」にぴったりの内容や文例をご紹介します。
12月ってどんな月?

12月は、1年のまとめと新しい年への準備が重なり、行事が多くにぎやかな季節です。発表会やクリスマス会、大掃除などを通して、子どもたちが仲間と協力したり、目標に向かって努力したりする貴重な経験を重ねる時期でもあります。
また、クリスマスのような楽しいイベントだけでなく、「冬至」に触れることで、季節の移ろいや古くからの慣習について伝える良い機会があります。園での活動としては、クリスマスに寄せた製作や歌などの活動のほか、かぼちゃやゆずを取り入れた食育などにも取り組むことができ、子どもたちの興味や知識の幅を広げていきながら、大きな成長が見られる月です。
その一方で、気温の低下とともに感染症が流行しやすくなるため、健康管理への配慮も欠かせません。冬休みを目前に控え、家庭でも元気に過ごせるよう、体調管理や生活リズムの大切さについて、ご家庭と連携していく必要性を伝えることも重要です。
大人が慌ただしくなりがちな時期だからこそ、園の中では子どもたちが落ち着いて過ごし、安心して1年を締めくくることができるよう丁寧に見守り、関わっていきましょう。

12月のおたよりづくりのポイント
季節や気候の変化によって、園から保護者に伝えたいことは異なります。また、保育士の目線で園からの連絡事項や最近の子どもたちの様子を伝えることは、おたよりの大切な要素です。
12月に保護者に伝えておきたいこと
- 発表会やクリスマス会など行事の案内
- 感染症の流行状況や対策の確認
- 年末年始の過ごし方のポイント
- 1年の成長を振り返るメッセージ
最近の園の様子
園庭や施設内の変化、先生たちの近況などについてお知らせしましょう。
- クリスマス会や発表会の準備が進められており、園内もにぎやかになってきました。
- 1年の成長を振り返る機会として、玄関や各保育室に写真や制作物の展示を始めています。どうぞお時間のあるときにご覧ください。
子どもたちの様子
最近の園における子どもたちの様子、成長が見えるエピソードなどを月齢別に紹介します。
乳児(0~2歳児)
クリスマスの音楽を流すと、曲に合わせて、自然と体を揺らして楽しむ様子が見られます。
風邪でお休みしているお友達のことを気にかけたり、登園したときに元気になったことを喜んだりする姿が見られ、成長を感じます。
幼児(3~5歳児)
発表会で使う鈴やカスタネットの使い方を、お友達同士で教え合って練習する姿が見られます。おうちの人に見てもらうことをとても楽しみにしています。
「プレゼント、もう決めた?」「サンタさんに手紙を書かなきゃ!」など、クリスマスについての話題が、子どもたちの間でも聞かれるようになってきました。
12月のおたより 書き出し・結び<文例>
季節を取り入れたおたよりの例文を紹介します。
書き出し
「子どもたちが待ちに待ったクリスマスが近づき、園内は少しずつにぎやかな雰囲気に包まれています。」
「今年も残すところ、あとひと月を切りました。イベントの多い12月ですが、子どもたちは変わらず元気いっぱいです。」
「早いもので今年もあとわずか。1年を締めくくる発表会に向けて、子どもたちは日々一生懸命練習しています。」
結び
「体調を崩しやすい時期でもありますので、健康面への配慮を続けてまいります。」
「1年の終わりに、ご家庭でも子どもたちの成長を振り返っていただけたらと思います。」
「今年も保護者の皆様からの温かいご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。どうぞよいお年をお迎えください。」
12月の行事紹介
暦に関する文例
12月22日 冬至

「冬至」は二十四節気の1つで、1年のうちで昼が最も短くなる日として知られています。毎年12月21日または22日とされており、この日にゆず湯に入ったり、かぼちゃを食べたりして健康を願います。ゆず湯は邪気を払い、体を温めて血行を良くし、風邪をひかないようにすると言われています。またかぼちゃは、保存がきく栄養価の高い野菜として、冬至に食べるようになったとされており、どちらも寒い季節を元気に過ごすための風習として、今も伝わっています。
園でもこの機会に、季節によって昼と夜の時間の長さが変わること、また風邪をひかないための入浴の習慣や食べ物の大切さについて子どもたちと話す時間を作り、伝統的な風習の意味を伝えていきます。
12月25日 クリスマス

クリスマスは、イエス・キリストの誕生を祝う日とされていますが、古くはヨーロッパで行われていた冬至のお祭りなど、さまざまな習慣が重なってできた行事とも考えられ、現在では宗教にかかわらず、世界中で楽しむ冬の行事として親しまれています。
子どもたちにとっても、ツリーや飾りつけ、サンタクロースの存在など、クリスマスは心を躍らせる一大イベント。園でも「サンタさんは来るかな?」「プレゼントは何だろう?」と楽しそうに話す姿が見られます。ご家庭でも温かな雰囲気の中で、クリスマスの思い出を作っていただければと思います。
12月31日 おおみそか

1年の最後の日であり、おうちでは大掃除をしたり、年越しそばを食べたりと、新しい年を気持ちよく迎えるための準備をする習慣があります。
園でもこの時期には、「1年間よく頑張ったね」と、子どもたちといっしょに一年の出来事をふり返りながら、いろいろな経験を重ねてきたことを言葉にして伝えています。自身の成長を感じたり、身のまわりをきれいにしたりする中で、「新しい年」を迎える心の準備も一緒に行っていきたいと考えています。
年末年始は生活リズムが乱れやすい時期でもあります。ご家庭でも無理のないペースで過ごしながら、良い年越しを迎えていただけたらと思います。
園の行事に関する文例
クリスマス会

子どもたちが楽しみにしている大きな行事のひとつです。みんなでクリスマスの歌を歌ったり、ゲームをしたりして楽しい時間を過ごしましょう。今はそれぞれのクラスで飾り付けの準備や、異年齢のクラスの子に贈るプレゼントの製作を進めており、園全体にクリスマスムードが漂っています。活動の中で、「この色がいいと思う!」「こうすれば気に入ってくれるかな?」など、積極的に自分たちで工夫したり、意見を出したりしている様子に、大きな成長を感じます。
当日は、先生サンタからみんなへのプレゼントタイムも予定しています!みんなで心温まる時間を過ごせるよう、準備を進めてまいります。
発表会

歌や劇、楽器演奏など、それぞれの年齢に合わせた表現に取り組み、その成果を発表します。役になりきったり、お友達と声を合わせたりする中で、協調性や自分を表現する力が育まれています。
本番では緊張しながらも一生懸命に頑張る姿を温かく見守っていただき、ご家庭と園とで、子どもたちの成長の喜びを一緒に分かち合える機会となればうれしく思います。
大掃除

年末には、園全体で「大掃除」を行います。子どもたちも保育室やロッカー、使っているおもちゃなどを、先生やお友達と一緒にきれいにしていきます。活動を通して、役割分担や協力の大切さ、物を大切に扱う気持ち、そして掃除をすると気持ちよく新年を迎えられるということを、子どもたち自身の体験として感じてほしいと考えています。
当日は汚れても良い服装での登園にご協力ください。活動内容は年齢に合わせて無理のない範囲で行い、楽しみながら1年の締めくくりにふさわしい時間を過ごしたいと思います。
12月のおたよりに添えられるネタ
季節の豆知識などをおたよりの1コーナーにすることで、おたよりが保護者にとっても楽しめる、親しみやすいものになります。
- 冬至の豆知識:「なぜゆず湯に入るの?」「かぼちゃを食べる意味は?」などをわかりやすく紹介。
- 年末年始の過ごし方ヒント:おうち時間が増える時期におすすめの工作・手あそびネタを紹介。
- クリスマス絵本ガイド:読み聞かせにおすすめの絵本や、園で人気の絵本を紹介。
まとめ
12月は年末に向けて、園の内外でもにぎやかな雰囲気が漂う季節です。クリスマスや発表会などのイベントを経験していく中で、子どもたちが大きな心の成長を見せることもあります。キラキラしたまなざしや、張り切っていた姿など、園での取り組みの様子をおたよりで家庭に伝えられると良いですね。年の最後は、園からの感謝の気持ちや、「また来年もよろしくお願いします」のひとことを添えて、心のこもったおたよりを届けましょう。