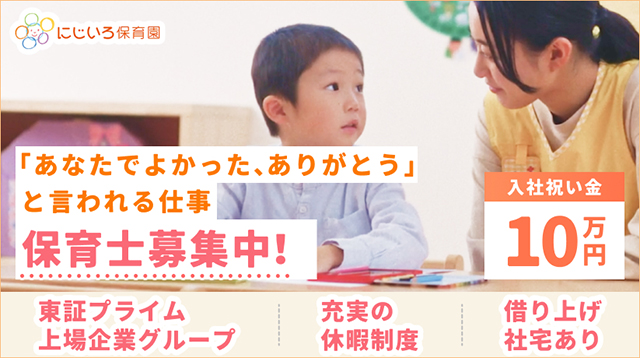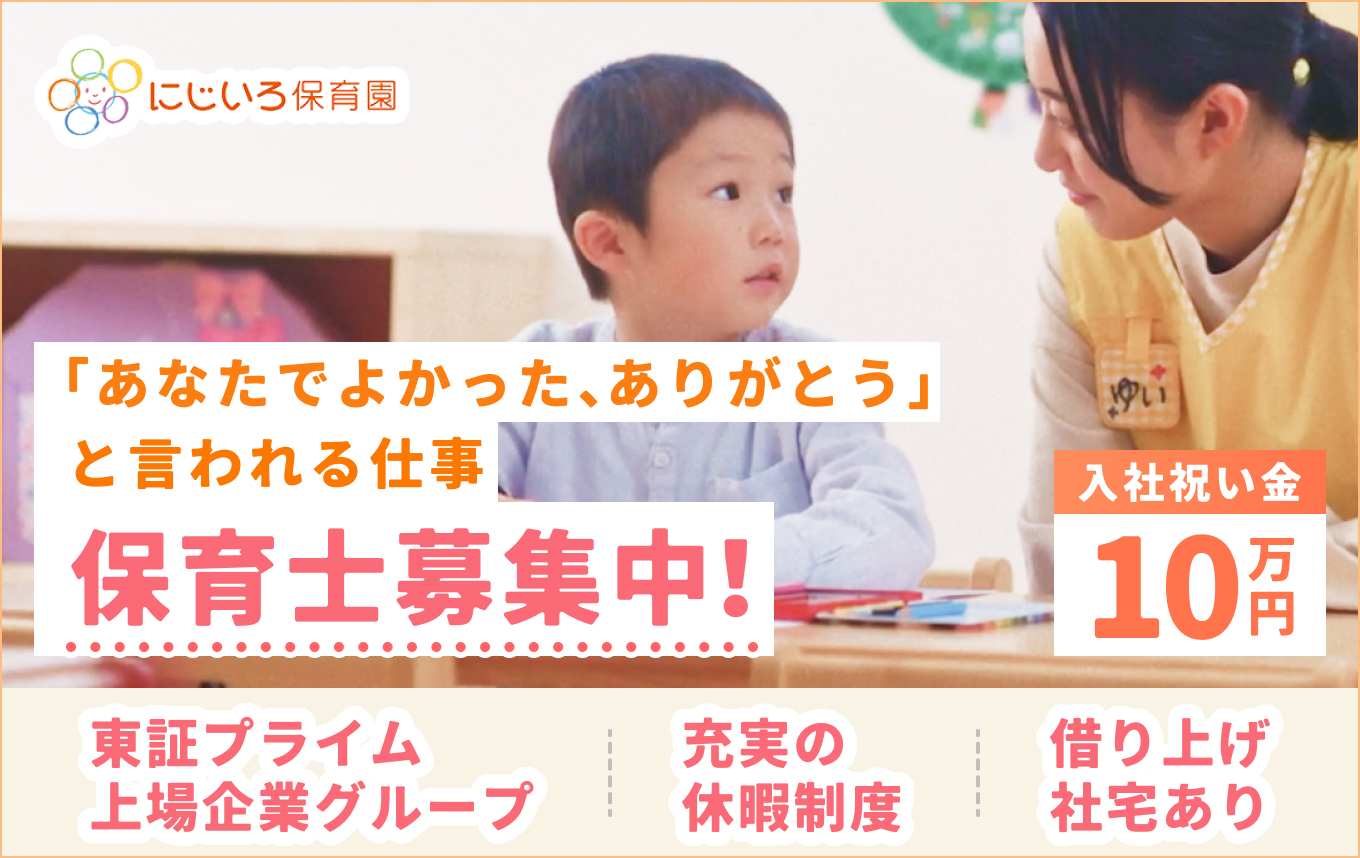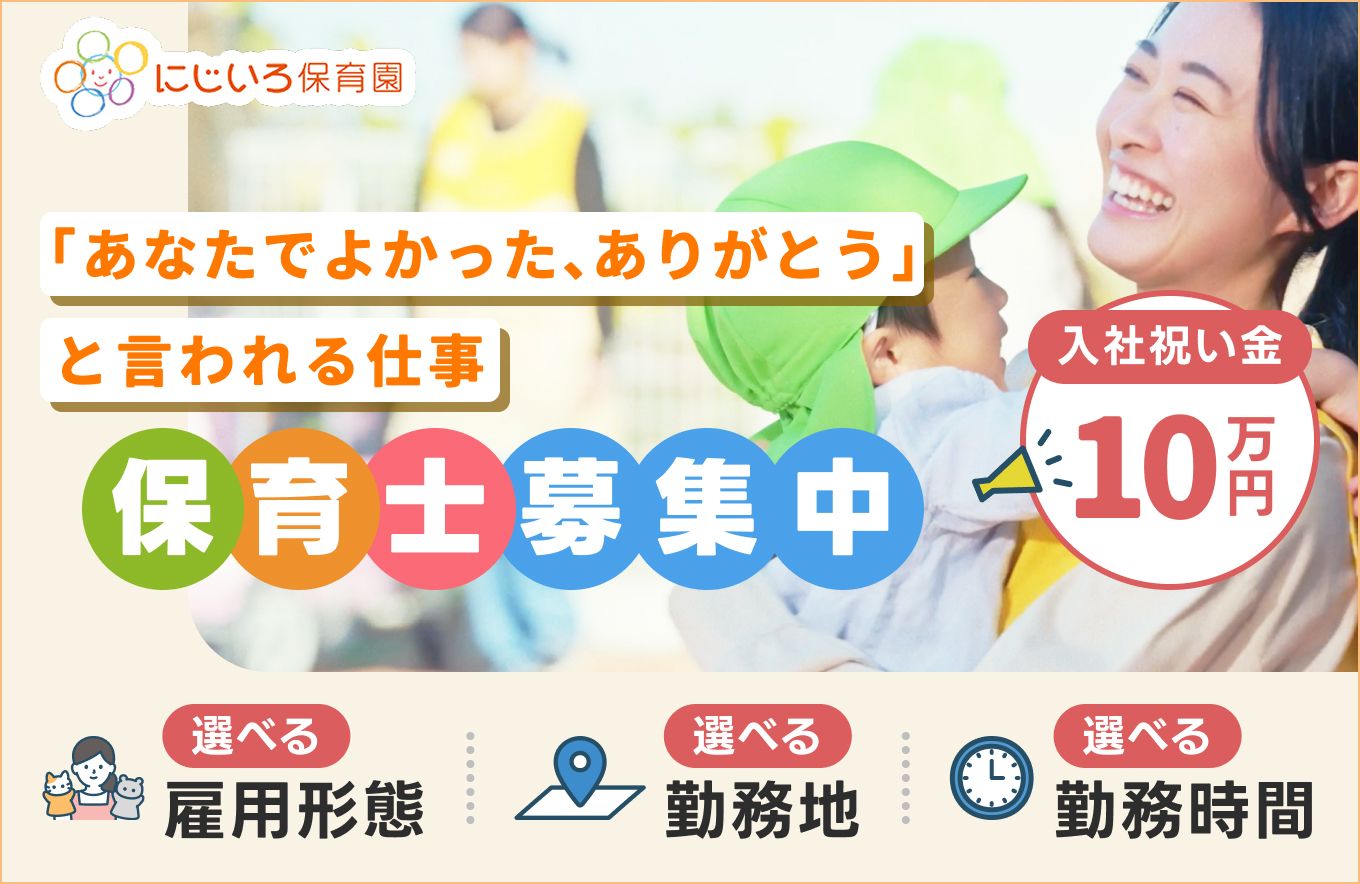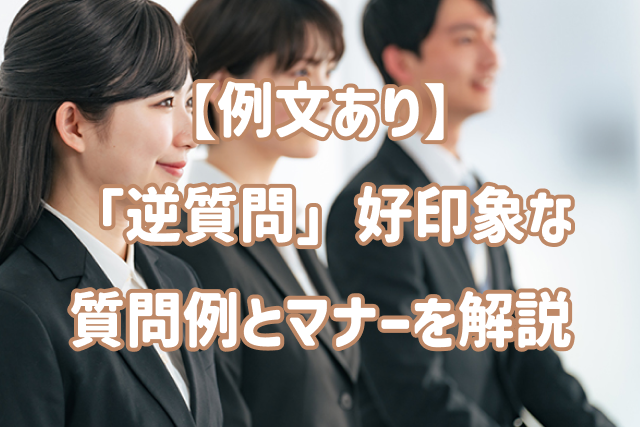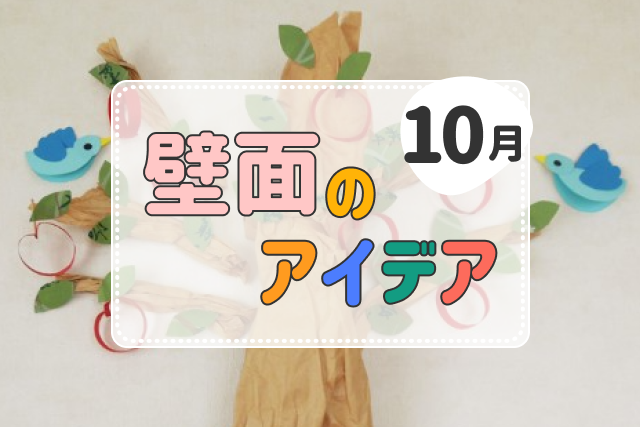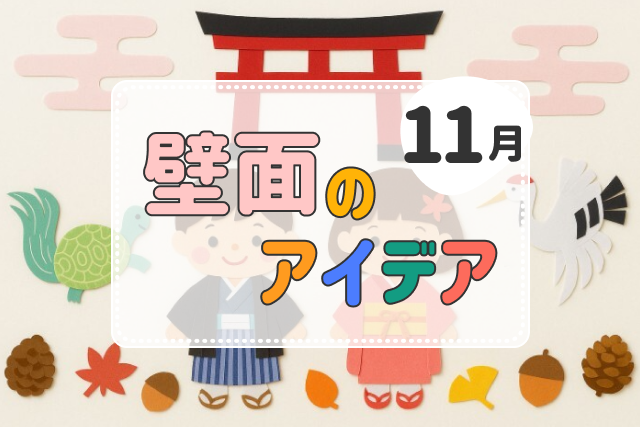2025.06.30
緊張しても大丈夫!保育実習の自己紹介で子どもと仲良くなるコツ
保育実習の初日は、実習生にとってドキドキの日。最初の「自己紹介」は、子どもたちとの距離をぐっと縮められるチャンスです。緊張していても大丈夫!言葉の選び方や表情、声の出し方など、少しの工夫で与える印象が大きく変わります。子どもの年齢別の伝え方や準備のポイント、つまずきがちな「あるある」の対処法などを紹介します。
自己紹介で「はじめまして」を成功させる3つのポイント

自己紹介の場面は、子どもたちとの関係づくりの第一歩。ほんの少しの工夫で、緊張が安心に変わります。無理なく、自然体で「はじめまして」を伝えるポイントを押さえておきましょう。
言葉の選び方:シンプルで伝わる表現にしよう
自己紹介では、「自分のことをしっかり伝えなきゃ」とつい難しい言葉や長い文章になりがちです。でも、子どもたちにとって大切なのは「わかりやすくて、イメージしやすい言葉」。「〇〇大学の〇〇です。よろしくお願いします」のような、難しい言い回しや敬語は避け、短くて親しみのある言葉が効果的です。「〇〇せんせいってよんでね。きょうからいっしょにあそぼうね」のように、やわらかい語尾を意識すると、子どもたちの心にも届きやすくなります。
表情と視線:笑顔とアイコンタクトで安心感を
緊張して視線が泳いだり、表情がかたくなったりしてしまうのは誰にでもあることです。でも、子どもたちは大人のちょっとした表情の変化をとても敏感に感じ取るもの。笑顔でいることは、それだけで「この先生、優しそう」「話しかけてみたい」という印象につながります。無理にニコニコする必要はありませんが、自然な笑顔と、子どもたちにやさしく目を向ける姿勢があるだけで、安心感や信頼が生まれます。特に年齢の低い子ほど、言葉よりも「表情の優しさ」が伝わりやすいので、落ち着いてゆったり子どもと向き合いましょう。
声の出し方:やさしく、はっきり伝える声を意識
保育の現場では「大きな声」よりも「届く声」が大切です。子どもに話しかけるときは、はっきりとした発音を意識しながらも、やわらかさや温かさが感じられるトーンを心がけましょう。語尾を少し伸ばしたり、「〜だよ」「〜してね」といった語りかけのような話し方にしたりすると、より親しみが生まれます。また、声のボリュームだけでなく、話すテンポや間の取り方にも意識を向けてみましょう。特に自己紹介の冒頭では、少しゆっくり話すと、子どもたちの集中力を引き出しやすくなります。
年齢に合わせた伝え方:子どもに響く自己紹介の工夫

子どもの発達段階によって、響く言葉や関わり方は少しずつ変わります。それぞれの年齢に合った伝え方を意識することで、より親しみやすい雰囲気を作ることができます。子どもたちの反応に耳を傾けながら、自分らしい言葉で「はじめまして」を伝えましょう。
0〜2歳児:まずは名前と笑顔で安心感を
言葉よりも表情や雰囲気が伝わるこの時期には、やさしい声と明るい笑顔がいちばんの自己紹介になります。「〇〇せんせいだよ」とゆっくり、リズムをつけて話しかけると安心感が増します。無理に言葉をかけすぎず、しゃがんで目線を合わせ、ゆったりとした動作で関わることも大切です。関係づくりは焦らず、繰り返しの関わりの中で築いていきましょう。
3〜4歳児:好きなものトークで親しみやすく
「せんせいは、いちごがすきだよ」「どうぶつならうさぎがすき!」など、自分の「好き」を伝えると、子どもたちとの距離が一気に縮まります。「〇〇ちゃんは何がすき?」と問いかければ、会話のきっかけにもなります。あいづちを打ったり驚いたりしながら、子どもの反応に興味を持って耳を傾けると、自然なやりとりが広がっていきます。
5歳児:問いかけで会話のキャッチボールを
「今日は何をしてあそびたい?」「おてつだいできるかな?」など、子どもたちとやりとりを楽しむような問いかけを意識してみましょう。年長児は話を聞いたり考えたりする力が育ってきているので、自身の個性や興味を交えて関わると、会話がふくらみやすくなります。相手に関心を持つ姿勢を見せることが、信頼関係づくりの第一歩になります。
自己紹介を成功に導く!安心の準備チェックリスト
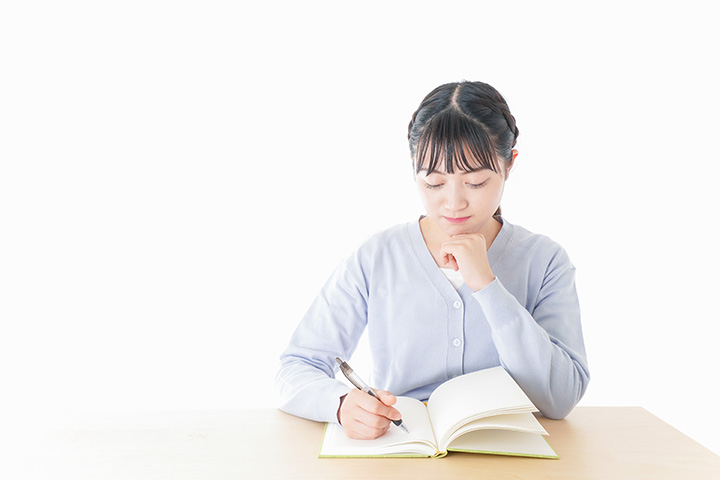
大切なのは「完璧に話す」ことではなく、「伝えたい気持ちが伝わる」こと。ちょっとした準備で心構えができ、自信を持って臨むことができます。そのための準備ポイントを3つに分けて紹介します。
話す内容を事前にメモして練習しよう
いきなり人前で話すと、緊張で頭が真っ白になってしまうこともあります。自己紹介では「名前・好きなもの・あいさつ」の3つを軸に、短い言葉でまとめておくと安心です。口に出して何度か練習しておけば、当日もスムーズに言葉が出てきます。時間に余裕があれば、実際の園生活を想定して「子どもに向けて話す」練習をしてみるとより効果的です。
鏡の前や録音で話し方をチェックしよう
どんなに内容が良くても、表情や声のトーンで印象は大きく変わります。鏡の前で練習すると、自分の表情や目線のクセに気付くことができるので、事前に確認してみましょう。また、スマートフォンなどで音声を録音し、聞き返してみると「語尾が小さい」「最初が早口になっている」など、自分の話し方の特徴をつかみやすくなります。「自分を客観的に見て直す」を繰り返すことで、落ち着いて自己紹介できるようになります。
当日の身だしなみも第一印象のカギ
子どもや実習先の保育士にとって「初めて会う実習生」の第一印象はとても大切です。髪形や服装、名札の付け方など、見た目に清潔感があると「安心できる人」という印象を持ってもらいやすくなります。奇抜なアクセサリーや香水などは避け、シンプルで整った印象を心がけましょう。また、マスクをつける場合も、声の明るさで気持ちが伝わるように工夫してみてください。
実習生が陥りがちな「あるある」失敗と解決法

実習初日は、誰でも緊張するもの。「思うように話せなかったらどうしよう…」という不安を抱えるのは当然です。ここでは、よくある「つまずきポイント」を取り上げ、それぞれに対する前向きな解決法を紹介します。失敗しても大丈夫!その後のリカバリーで、子どもとの関係がより深まることもあります。
緊張で棒読み…自然に話すにはどうすれば?
頭ではわかっていても、いざ子どもたちの前に立つとガチガチに緊張して、用意した自己紹介を棒読みになってしまうこともあります。完璧に話そうとせず「気持ちを込めて伝える」ことを意識しましょう。練習では「感情をのせて話す」ことも意識してみると、本番でも表現が自然になります。少しくらい言い間違えても、にっこり笑えば子どもたちはしっかり受け止めてくれます。
言葉に詰まった…自己紹介が飛んでしまったら?
話の途中で「あれ?次なんだっけ?」と止まってしまうこともあるかもしれません。そんなときは、一度深呼吸して仕切り直せばOK。「ちょっと忘れちゃった!えへへ」と笑いながら続けるだけでも、子どもたちは「素の姿」に親しみを持ってくれます。事前に短く要点をまとめておくことで、万が一のときも思い出しやすくなりますよ。
声が小さい・笑顔が引きつる…そんなときは?
自信がないと声が小さくなったり、笑顔がぎこちなくなったりしがちです。でも、無理に声を張り上げたりせず、目の前の子ども1人に語りかけるつもりで、ゆっくり話してみましょう。「自分が注目されている」のではなく、「仲良くなりたい子どもに向かって話している」と意識を切り替えることで、声のトーンや表情も自然にやわらぎます。
自己紹介にひと工夫:子どもとの距離をぐっと縮める方法
自己紹介に、ちょっとした「遊び心」を加えると、子どもたちはぐっと親しみを感じてくれます。話すだけでなく、「見せる」「一緒にやる」要素を取り入れることで、子どもの関心を引きつけ、楽しい雰囲気を作ることができますよ。簡単に取り入れられるおすすめの工夫を紹介します。
手遊び例:「グーチョキパーで何作ろう?」
誰もが知っている手遊びを自己紹介に組み込むと、一気に場がなごみます。例えば、「グーチョキパーで何作ろう?」を一緒にやりながら、「これなーんだ?」と子どもたちにクイズ形式で問いかけていくと、子どもたちもいっしょに考えて盛り上がることがおでき、楽しい印象が残ります。コミュニケーションの最初の一歩になり、その後の活動にもスムーズに入っていけますよ。
視覚で伝える例:絵カード・写真で「好きなもの」を紹介
まだ言葉でのやりとりが難しい年齢の子どもには、視覚的なツールが効果的です。自分の「好きな食べ物」や「好きな動物」などのイラストを描いたカードを見せながら紹介すると、子どもたちはぐっと注目してくれます。絵が得意でなくても、手描きの温かさが伝わりますし、子どもとの共通点を見つけるきっかけにもなります。
まとめ
初日は誰でも緊張するもの。でも、子どもたちは実習生にとても関心を持っています。
うまく話すことよりも、「感じ良く伝わること」が自己紹介のカギ。ちょっとした工夫で「自己紹介」は「話す時間」から「心をつなぐ時間」へ変わります。「仲良くなりたい」という気持ちを大切に、笑顔ではじめの一歩を踏み出してみてください。
事前に実習先の園を訪問する機会があれば、先輩保育士たちの表情や声かけの様子を見て、参考にしましょう。
ライクキッズが首都圏を中心に150園以上運営している「にじいろ保育園」では、園見学を受け付けています。保育の現場を実際に見て、働くイメージをふくらませてみませんか?