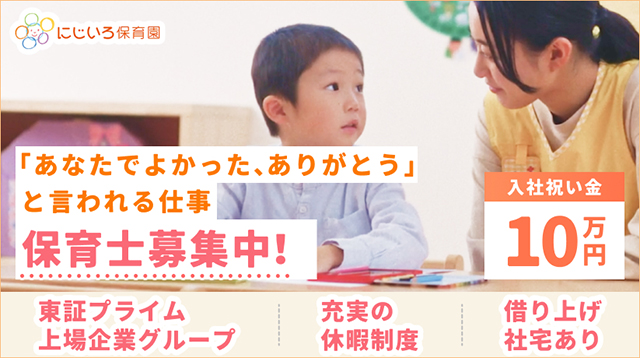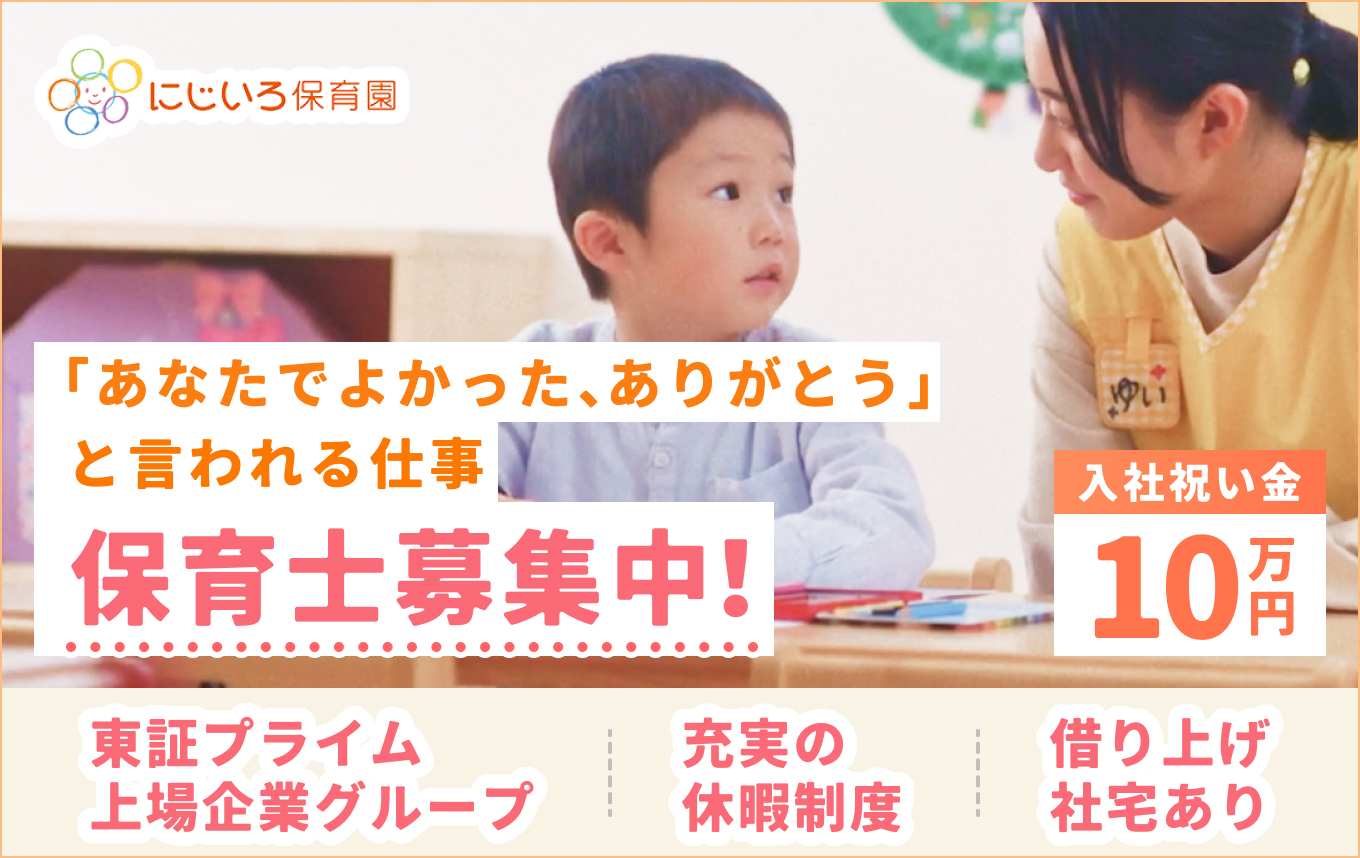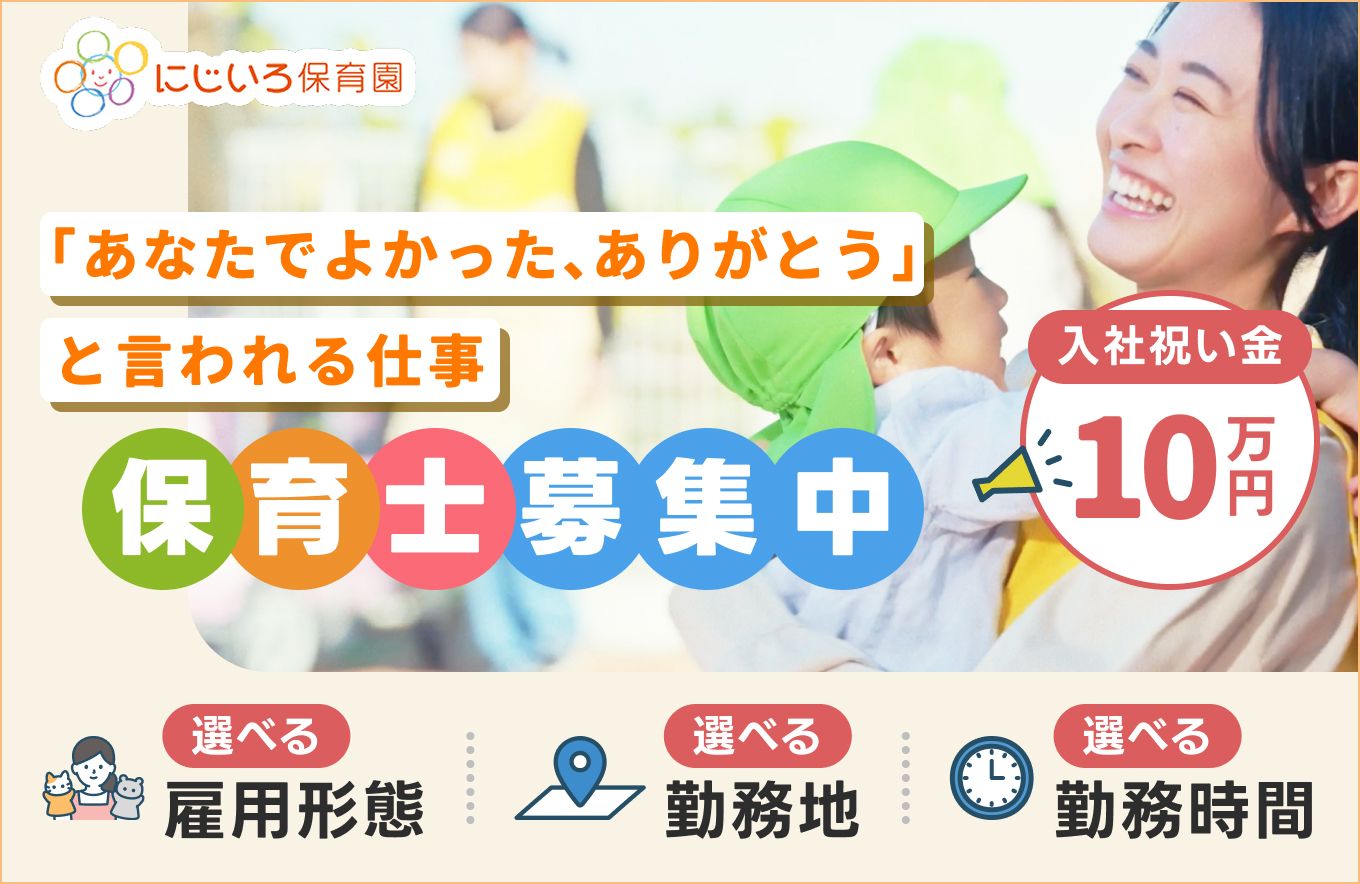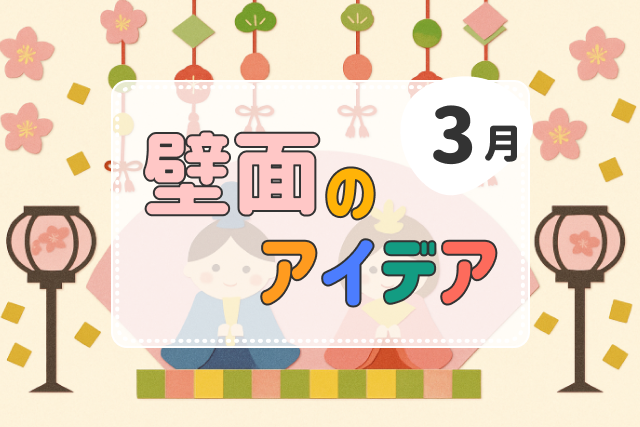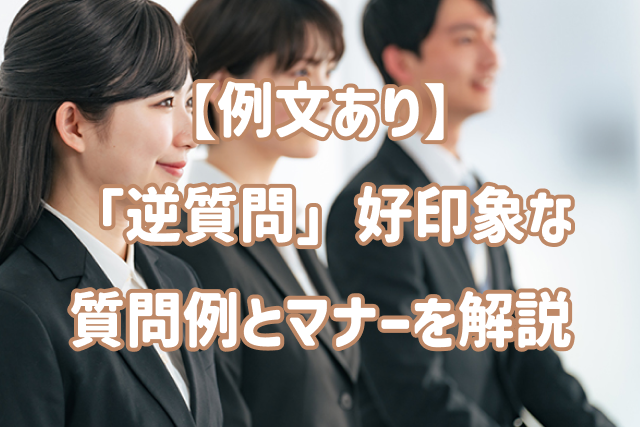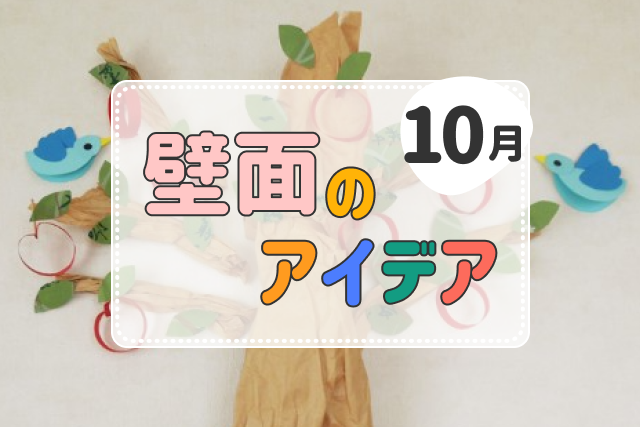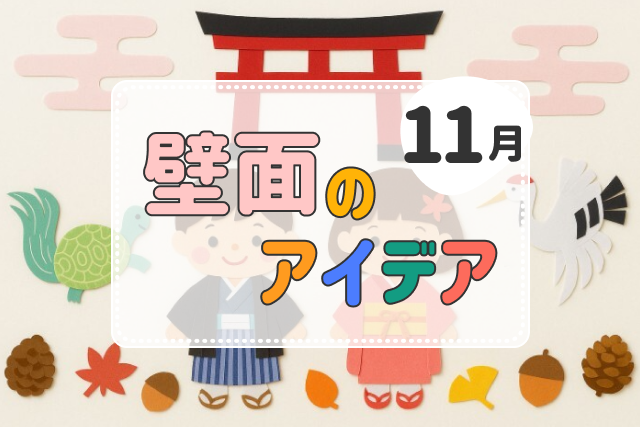2025.07.01
【2025年版】保育士資格の取り方と必要なステップをわかりやすく解説
「将来、子どもに関わる仕事をしたい」「保育士って、どうやって資格を取るの?」保育士になるためには、指定の養成施設を卒業するルートと、国家試験である「保育士試験」に合格するルートの2つがあります。それぞれの特徴や必要な条件、試験の手続きの流れをわかりやすく解説します。
保育士資格とは?

保育士資格とは、児童福祉法に基づいて定められた国家資格で、保育所や児童福祉施設などで子どもの保育を行うために必要な資格です。主な役割は、0歳から小学校就学前の子どもたちの健やかな成長を支えること。食事・排泄・睡眠などの生活習慣のサポートはもちろん、遊びや集団活動を通じて社会性や自立心を育む手助けを行います。
保育士は単なる「子守り」ではなく、家庭や社会との連携を図りながら、子ども一人ひとりの発達段階に応じた保育を行う専門職です。そのため、厚生労働大臣の指定する試験または認可施設の卒業により国家資格を取得する必要があります。保育士資格は、子どもと関わる仕事の中でも高い専門性が求められるものであり、信頼と責任を伴う職業の入り口と言えるでしょう。
保育士資格の取得方法は2通り

保育士資格を取得する方法は、大きく分けて「指定保育士養成施設の卒業」と「保育士試験の合格」の2通りがあります。
指定保育士養成施設を卒業する
厚生労働大臣または都道府県知事の指定する保育士養成施設(大学・短期大学・専門学校など)を卒業することで、申請により保育士資格を取得できます。カリキュラムには理論と実技を組み合わせた内容が含まれ、保育の基礎から実習までを体系的に学びます。
保育士試験に合格する
保育士試験は、年2回実施される国家試験です。都道府県知事が実施し、筆記試験と実技試験をいずれも合格する必要があります。受験資格は学歴や実務経験などにより異なり、合格後は登録手続きを行うことで保育士資格が付与されます。
保育士試験の受験資格と申請方法

保育士試験の主な受験資格は以下の通りです。
- 【大学・短期大学卒業/在学中】
- 【専門学校卒業】
- 【高等学校卒業】
- 【中学卒業・高校中退など】
原則として受験資格あり(専攻や課程不問)
「学校教育法に基づいた専修学校」であり、卒業した課程が修業年限2年以上の専門課程であること
上記2点のうち1点満たされていない場合でも、高等学校の卒業が平成3年3月31日以前または保育科なら平成8年3月31日以前であれば受験資格あり
平成3年3月31日以前、保育科なら平成8年3月31日以前であれば受験資格あり
もしくは高校卒業後、児童福祉施設等での実務経験が「2年以上かつ2,880時間以上」あること
児童福祉施設等での実務経験が「5年以上かつ7,200時間以上」あること
受験資格を証明するには、卒業証明書や勤務証明書などの必要書類を用意する必要があります。
試験の申込みは、全国保育士養成協議会が年に一度募集を行い、原則として郵送での書類提出が求められます。申し込みには認定証や本人確認書類、顔写真なども必要です。
保育士試験の内容と対策

保育士試験は、筆記試験と実技試験の2段階に分かれて実施されます。筆記試験の合格者が、後日行われる実技試験に進むことができます。
筆記試験
筆記試験は以下の8科目で構成されており、それぞれに合格基準が設けられています。
- 保育原理
- 教育原理及び社会的養護
- 子ども家庭福祉
- 社会福祉
- 保育の心理学
- 子どもの保健
- 子どもの食と栄養
- 保育実習理論
筆記試験はマークシート方式で、すべての科目において100点満点中60点以上の得点で合格です。ただし、「教育原理及び社会的養護」はそれぞれ50点満点とされ、各30点以上の得点で合格となります。
一度の試験ですべての科目に合格する必要はありません。科目ごとの合格は原則合格した年を含めて3年間有効となるので、3年以内に全科目に合格すれば、実技試験に進めます。
また対象施設において対象期間内に所定の勤務期間および勤務時間、児童等の保護に従事した場合、最長5年まで延長できる制度もあります。
実技試験
筆記試験の全科目に合格した人のみが受験可能です。
以下の3分野のうちから任意で2分野を選択し、受験します。
- 音楽表現に関する技術(ピアノなどで童謡の弾き歌い)
- 造形表現に関する技術(課題に応じた絵画制作)
- 言語表現に関する技術(3歳児向けに3分程度のお話を口演)
保育士登録と保育士証の取得
保育士養成施設を卒業したり、保育士試験に合格したりしただけでは、すぐに保育士として働けるわけではありません。正式に保育士となるには、都道府県知事への「保育士登録」の手続きを行い、「保育士証」の交付を受ける必要があります。
保育士登録申請手続きを行うには、申請書や記入例などがセットされている「保育士登録の手引き」が必要です。登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を取り寄せ、申請書と共に「指定保育士養成施設卒業証明書」または「保育士試験合格通知書」などの資格を証明する書類と、現在の戸籍抄本を送付します。郵便局で1人当たり4,200円の登録手数料の払い込みを行い、その際の振替払込受付証明書も同封します。
登録が完了すると、「保育士証」が本人に交付されます。保育士証は全国で有効な国家資格の証明書であり、就職活動や現場での資格確認に用いられます。
登録後、書類に不備がなければ約2か月程度で保育士証が交付されます。
保育士資格取得後のキャリアパス
保育士資格を取得すると、保育所だけでなく、さまざまな児童福祉施設や教育関連機関で働くことが可能になります。キャリアのスタート地点は「保育士」としての現場業務ですが、経験を重ねることで管理職や専門職への道も開かれています。
■ 主な勤務先と業務内容
- 保育所(認可・認可外):乳幼児の保育と保護者対応、発達支援など
- 保育所(認可・認可外):乳幼児の保育と保護者対応、発達支援など
- 児童養護施設・乳児院・障害児施設:福祉的支援が必要な子どもたちへの専門的な保育
- 児童養護施設・乳児院・障害児施設:福祉的支援が必要な子どもたちへの専門的な保育
保育士は正社員だけでなく、パート・契約・派遣・フリーランス(ベビーシッターやイベント保育)など多様な働き方が可能です。また、在宅ワークと組み合わせた絵本制作・保育教材開発などの道も注目されています。
さらに、経験を活かして児童発達支援管理責任者や保育教諭(幼稚園教諭+保育士)といった他資格との連携によって、より幅広い分野での活躍も可能です。
まとめ
保育士になるための道は、学校を卒業して資格を得る方法と、試験に合格する方法の2通りがあります。ライフスタイルや学歴、働きながらの学び方など、自分に合ったルートを選ぶことが大切です。あなたも自分らしい方法で、保育士への一歩を踏み出してみましょう!