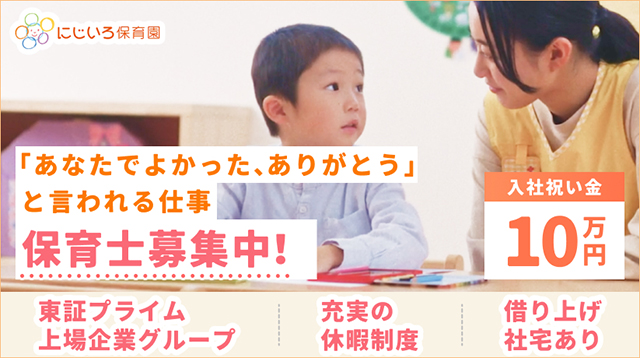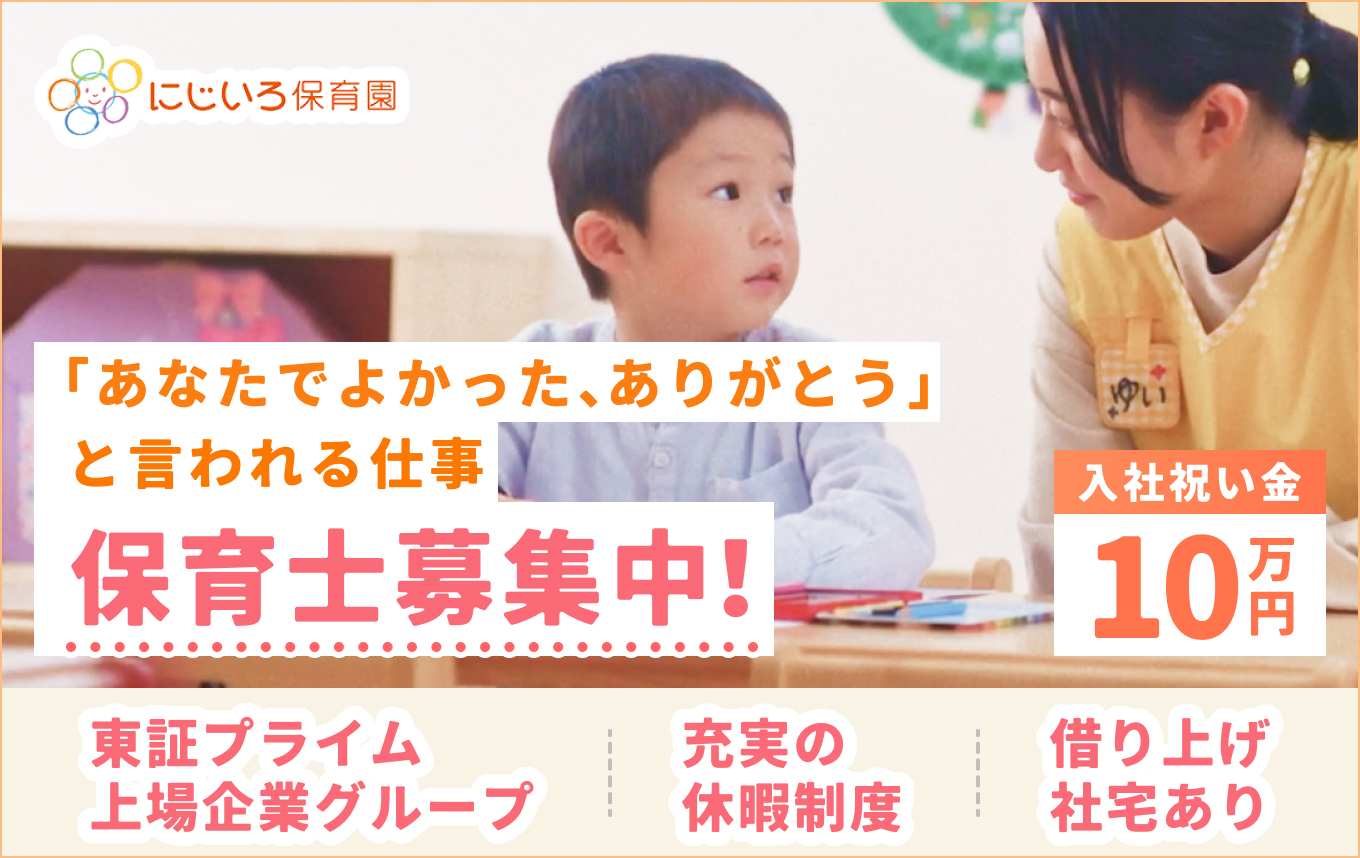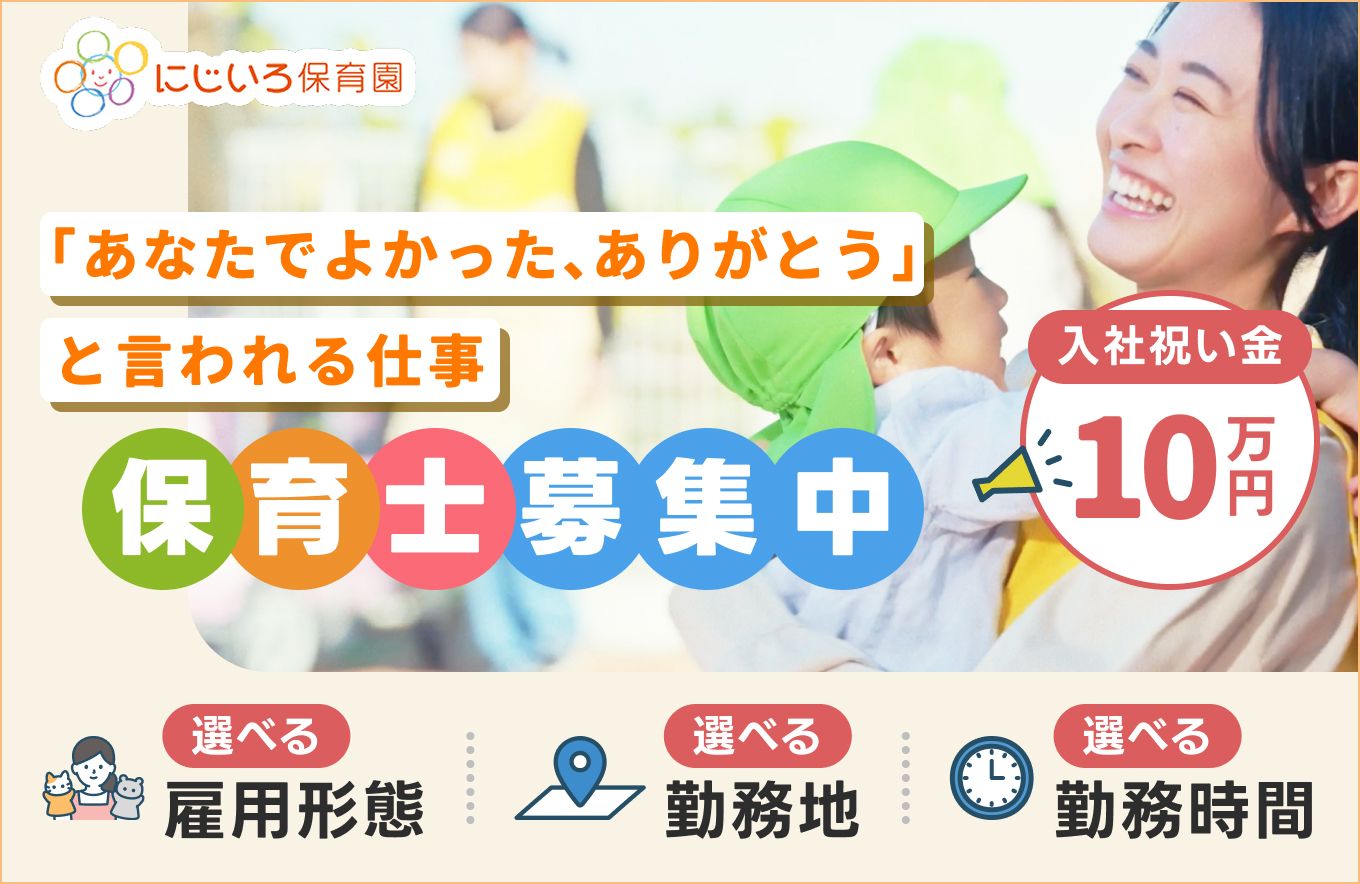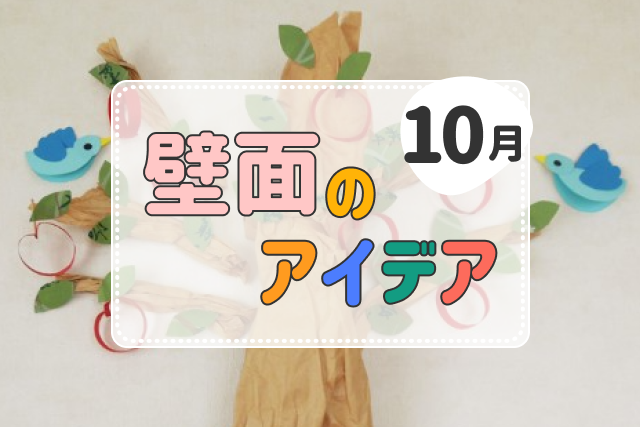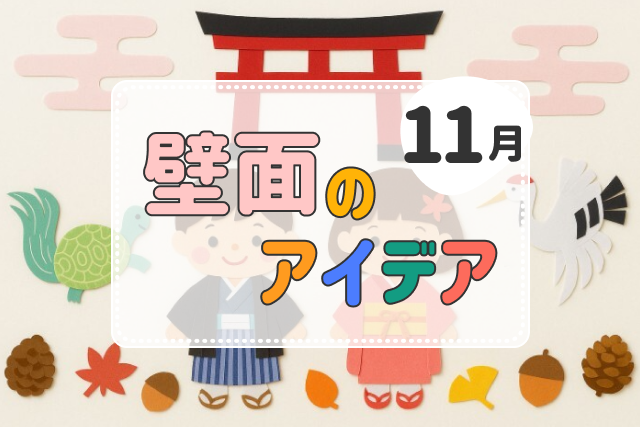2025.11.13
連絡帳ってどう書くの?知っておきたいポイントを例文付きで解説
保育園に入園すると、連絡帳の存在に戸惑う方も多いのではないでしょうか?
園からの連絡帳に対し、「毎日何を書けばいいの?」「こんな書き方で大丈夫かな?」と悩む保護者の方も少なくありません。この記事では、連絡帳の役割や書き方のコツ、例文や注意点をわかりやすく解説します。
負担に感じることがある連絡帳も、保育士が知りたい内容や無理なく続けられる書き方を知ることで、連絡帳を上手に活用でき、育児がより楽しくなりますよ。
連絡帳ってなに?

連絡帳は、保育園と家庭をつなぐ大切な情報共有ツールです。少し前までは、手書きでやり取りされることが主流でしたが、最近ではアプリを利用する園も増えています。形式は違っても、連絡帳の役割は同じ。保護者の方が園での子どもの様子を知るだけでなく、家庭での生活リズムや体調の変化を伝えることで、保育士がより安心・安全に子どもに向き合えるようにする役割を持っています。特に0歳〜2歳の子は、自分のことを言葉で伝えるのが難しい時期です。そのため、保護者が代わりに家庭での様子を伝えることがとても重要になります。
保育士が連絡帳で見ているところは?

「今日の連絡帳は何を書こう…」と悩む方は、まず保育士が知りたい情報をおさえると良いでしょう。実際に保育士は以下の5つのポイントに注目し、連絡帳を確認しています。
- 食事:朝食や夕食の量、食べた内容、食欲の有無。
- 睡眠:何時に寝て、何時に起きたか。夜中に起きたかどうか。
- 排泄:排便の有無や状態。下痢・便秘なども重要。
- 体調:熱、咳、鼻水、けがなど。
- 機嫌や家庭での様子:朝から不機嫌だった、好きなおもちゃで遊んでいた、新しい言葉を話したなど。
これらの情報があるだけで、保育士は園での子どもの小さな変化にも気づきやすくなり、関わり方を工夫することができます。
0歳〜2歳児クラスの連絡帳は「生活の情報」がカギ

0〜2歳の未満児は、家庭での生活リズムや体調を伝えることが、連絡帳の大きな役割となります。
たとえば「昨夜は寝つきが悪く、寝不足ぎみです」と書かれていれば、保育士はお昼寝の時間に配慮できます。また、「朝ごはんをほとんど食べませんでした」とあれば、食事時間を決める際の参考になります。
保護者が「こんなこと書いていいのかな?」と些細に思うことでも、園で過ごす子どもの安全や安心につながる大切な情報となるのです。
連絡帳に書く内容の例文集

ここでは実際に連絡帳に書く内容を例文をあげてご紹介します。
食事の例
- 「朝から食欲があり、7時ごろにパン1枚とバナナ1本を食べました」:しっかり朝食を摂ってきたことがわかる。朝食時間が書いてあることで昼食時間の目安になる。
-
「今朝は食欲がなく、牛乳だけ飲みました」:活動中にお腹が空き、不機嫌になることが予想できる。機嫌に応じて対応を検討する。
睡眠の例
- 「いつも通り20時〜7時まで眠りました」:普段の園の生活リズムで過ごせることを確認できる。
- 「いつも通り寝ましたが、夜中に2回起きて泣きました。少し寝不足ぎみです」:活動中に眠くなり、不機嫌になることが予想される。機嫌に応じて午前中に仮眠をしたり、食事やお昼寝を早めるといった対応をする。
体調の例
- 「鼻水が出ていますが、熱はありません。念の為、外あそびは控えてください」:体調の変化を気にかけ、園での様子を保護者の方に伝えることができる。また、外あそびの有無が書かれていると、保育士の配慮事項が明確でわかりやすい。
- 「お腹がゆるく、少し下痢気味です。乳製品は控えてください」:下痢は漏れやオムツかぶれの原因になる為、こまめにチェックして交換する。また、感染症を予想して、換気を行うなど二次感染予防に努める。
体調不良により控えて欲しい食品がある場合は、その旨を連絡帳に書くことで、保育士と栄養士が連携を測ることができる。場合によっては代替品を提供できるケースもあり。
機嫌や家庭での様子の例
- 「昨日から少しぐずっています」:体調の変化を気にかけ、経過観察をすることができる。
- 「昨日は初めて『おかあさん』と言いました!」:保育士と子どもとのコミュニケーションにつながる。「おうちで『おかあさん』って言ったの?お母さんうれしいね」などと、家庭の内容から会話がうまれる。
このように、具体的に書かれていることで、保育士は子どもの状態をイメージ・対応しやすくなります。
連絡帳を書く時の注意点

保護者の方と保育士とをつなぐ大切な連絡帳ですが、注意点もいくつかあります。
無理をしない
毎日連絡帳に長文を書く必要はありません。忙しい時は「元気です」や「特に変わりなし」だけでも十分伝わりますよ。
事実を簡潔に書く
「夜泣きがありました」「鼻水が少し」など、ありのままを書きましょう。一般的に保育士が連絡帳を記入するのは昼以降が多いですが、配慮事項などの確認のため、朝の活動前に一度目を通すことが多いです。この時に長文だと大切なことが伝わりづらくなります。
保育士にお願いしたいことははっきり書く
「朝、先生に伝えたから大丈夫!」と安心していませんか?保育士は毎日沢山の子どもを見ている為、口頭だけでは、捉え方の違いや連絡の行き違いなどによりトラブルにつながる可能性も考えられます。お互いが嫌な思いをしないためにも、お願いしたいことは忘れずに連絡帳に書きましょう。書くことで、いつでも確認できますよ。
連絡帳に関してよくある質問

連絡帳の書き方についてよくある質問をご紹介します。
Q.書くことが見つからない日はどうしたら良い?
A.「今日も元気です」だけで十分です。一言だけでも反応があることで、保育士は園からの連絡を読んでもらったことを確認できます。
Q.家での可愛い出来事を書きたい!長文になっても大丈夫?
A.もちろんです。連絡帳に家庭での様子が沢山書かれていると、その分子どもとのコミュニケーションはもちろん、保育士と保護者の方の関わりのきっかけにもなります。しかし、配慮事項がある場合は必要な情報を簡潔に書くと保育士に伝わりやすくなるでしょう。「今日は子どもの可愛かった出来事を連絡帳に書こう!」や「今日は、薬を飲ませて欲しいから簡単に注意事項をかいておこう」など書く内容によって使い分けるのがおすすめです。
Q.書き忘れたらどうする?
A.問題ありません。余裕がある時に無理のない範囲で書いてみてくださいね。
まとめ
連絡帳は、保育園と家庭をつなぐ大切な役割を担っています。特に0歳〜2歳の時期は、子どもが言葉で伝えられない分、家庭での生活リズムや体調を記録することが保育士にとって大きな助けになりますよ。
ぜひ例文を参考にしながら、無理なく書いてみてくださいね。書いた連絡帳を後で見返すことで、子どもの成長を感じて懐かしくなるときもあるでしょう。書けない日があっても大丈夫。子どもの成長を保護者の方と園とで共有できる安心のツールとして、ぜひ活用してみてくださいね。
執筆:原島円