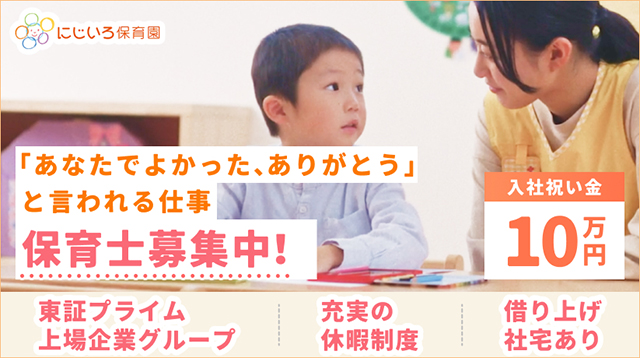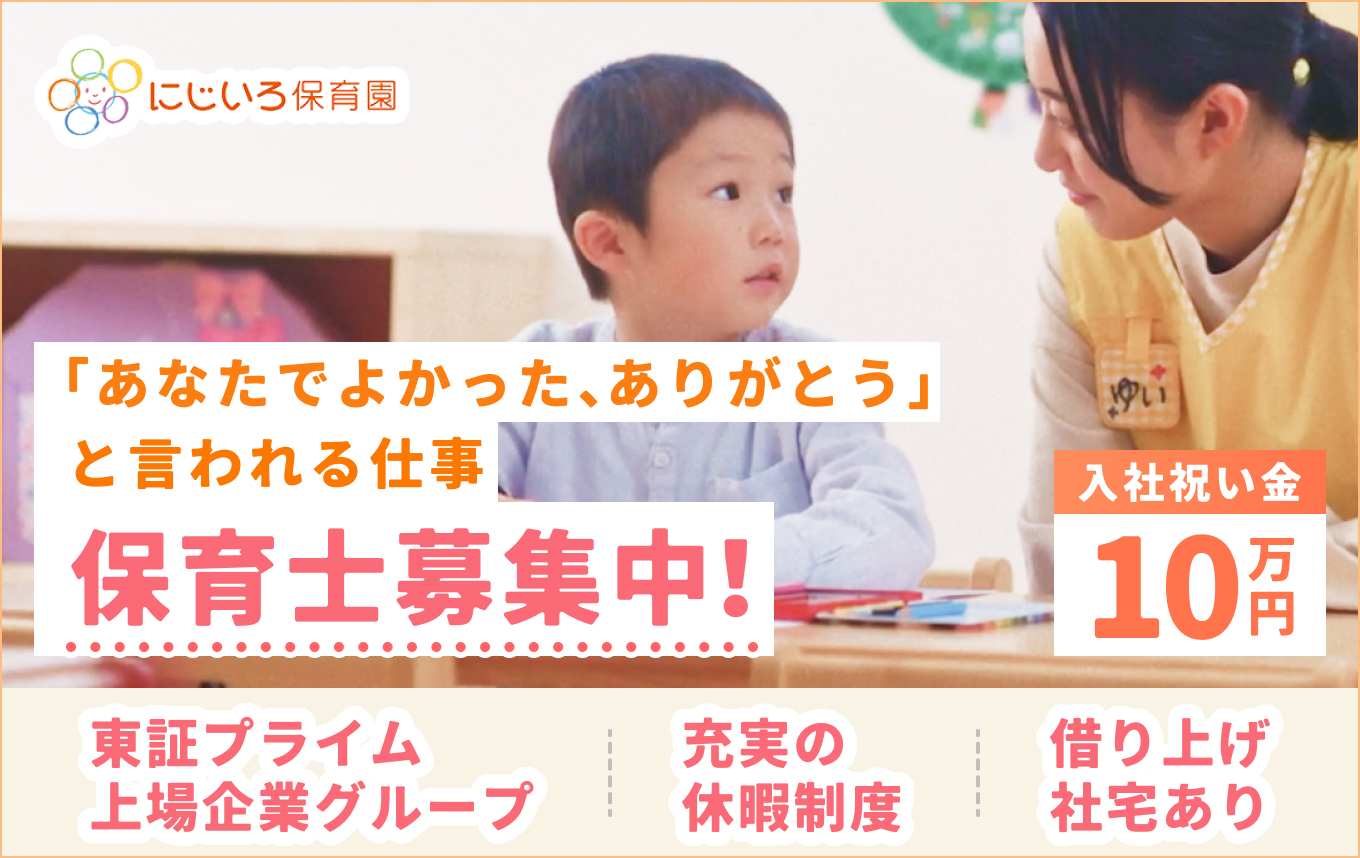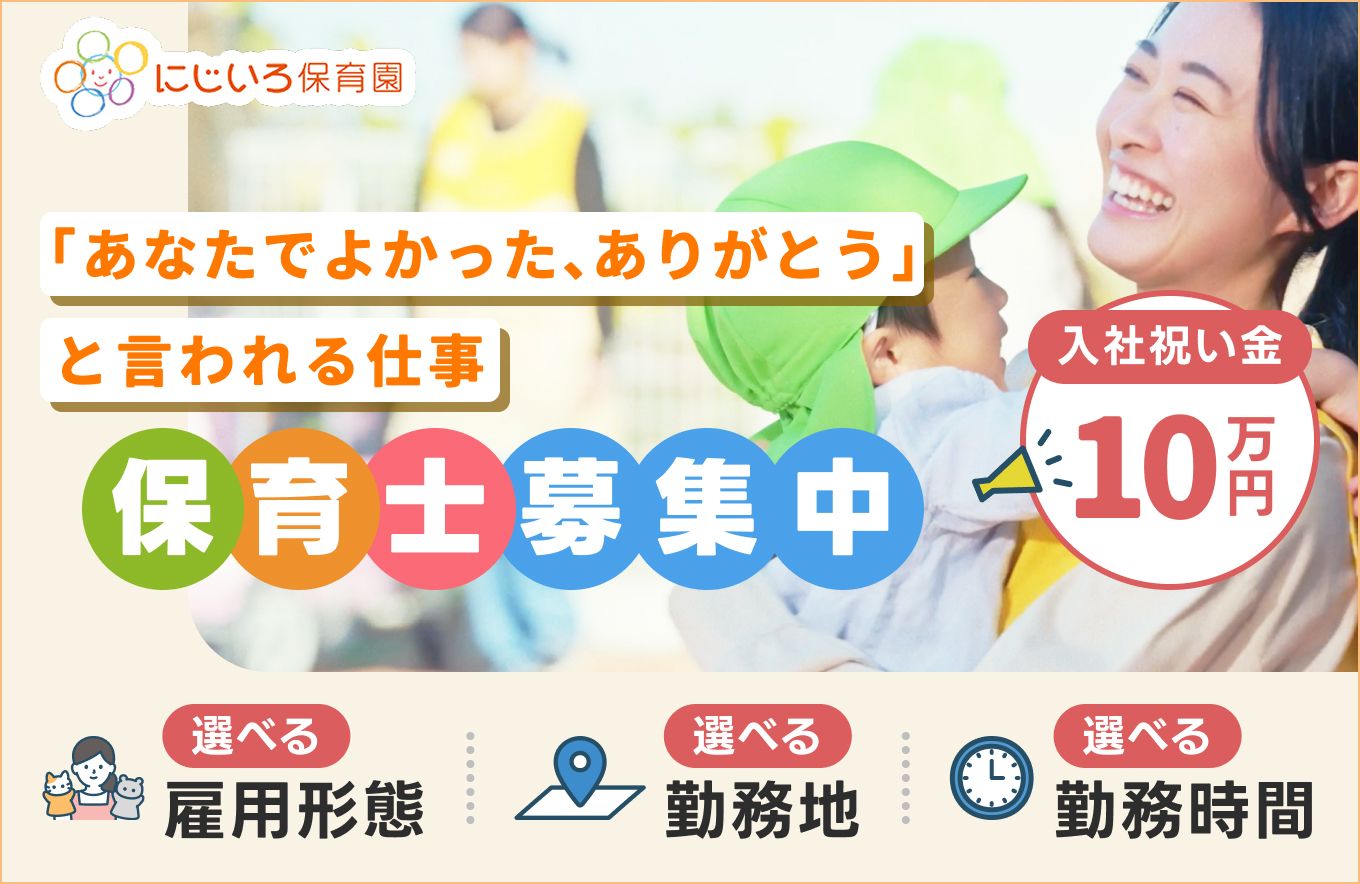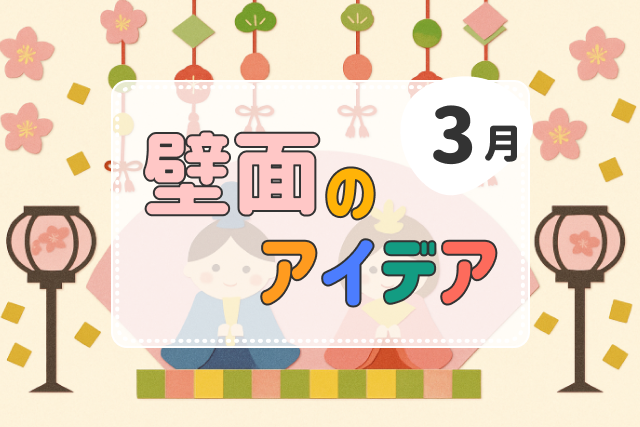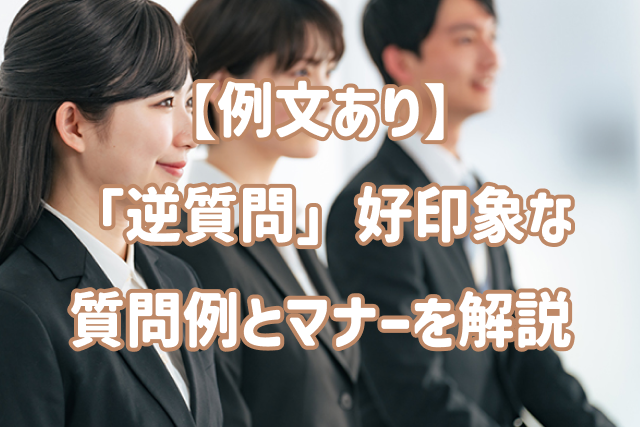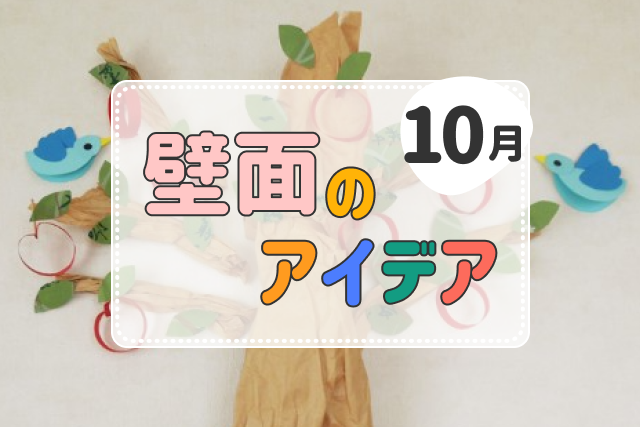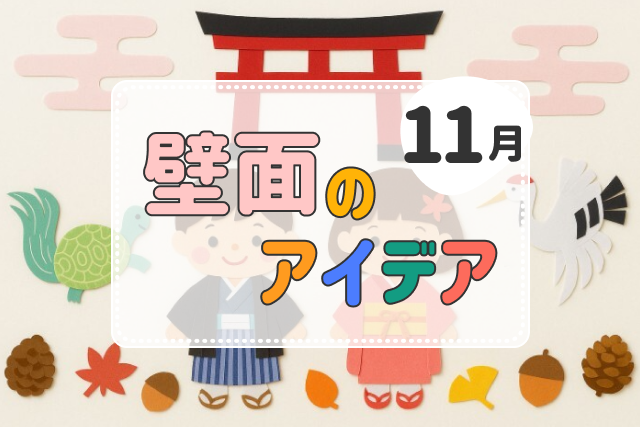2025.10.27
【保育園の12月遊び】ねらいが立てやすい!季節を楽しむ活動アイデア集
寒さが増す12月こそ、戸外でのびのびと体を動かすことで、冷たい空気の中で体を動かす心地よさが感じられる季節です。友達と力を合わせて楽しむ遊びや、役割分担のある遊びを通じて、子どもたちの心身はぐんと成長します。この記事では、12月にぴったりな遊びのアイデアと、遊びの「ねらい」についてご紹介します。
12月遊び「ねらい」の立て方のヒント

行事やイベントで、集団としての行動も増える12月。この月の遊びのねらいを立てる際は、「友達や保育士と関わりながら協力すること」「冬の寒さに親しみ、体を十分に動かすこと」を大きな柱にすると考えやすくなります。
乳児(0~2歳児)には、保育士と一緒に体を動かす心地よさや、リズムに合わせて体を動かす楽しさを味わうことをねらいとします。
幼児(3~5歳児)には、ルールや役割を理解して取り組む遊びを通じて、周囲を見て判断する力や協調性、勝ち負けを経験して気持ちを切り替える力を養ったりすることが期待できます。
年末にかけては生活のリズムや感染症の流行も考えられるので、衣服の調節などの体調管理について、遊びと結びつけて伝えることも大切です。
12月のおすすめ遊びアイデア
12月におすすめの遊びを、対象年齢の目安や年齢や成長に沿った遊び方、「遊びのねらい」などと共にご紹介します。
しっぽとり遊び「先生のしっぽとり」

「しっぽとり」は、腰につけた布やひもを「しっぽ」に見立てて取り合う遊びです。他の人のしっぽを取るために走ったり、自分のしっぽを取られないようによけたりするシンプルなる動きで、寒い冬でも体がしっかり温まります。ルールが分かりやすく、少人数から大人数まで楽しめるのが魅力です。
ただ低年齢児には、「取る」と「取られないようにする」の2つを同時に行うのが難しいかもしれません。 「先生のしっぽとり」は、しっぽをつけた保育士を子どもたちが追いかける、よりシンプルなやり方なので低年齢児にも楽しめます。複数の保育士がしっぽをつけたり、何本もしっぽをつけたりすることで、遊びが続けやすくなります。
対象年齢
2~3歳児
基本のルール
- しっぽになるものを用意する。(スズランテープや結んだなわとびなど)
- 保育士はズボンの後ろ側にしっぽをはさむ。複数人がしっぽをつける場合は、ズボンから出しておくしっぽの長さが全員同じになるようにする。
- 合図で一斉にスタートし、相手のしっぽを取ったら勝ち。取られたら負け。
- 複数人がしっぽをつける場合は、最後の1人になるまで、または制限時間がきたら終了。
遊び方のバリエーション
- チーム戦しっぽとり(3~5歳児向け)
「保育士VS子どもたち」のチームに分かれ、制限時間内に相手チームのしっぽをより多く取ったチームが勝ちとなるルールです。各チームの色のしっぽ(スズランテープなど)を用意し、配って一斉にズボンにセットすると、チーム戦の気分が盛り上がります。あらかじめ、走り回って良い範囲に線を引いておき、「しっぽを取られた子はすみやかに枠外に出る」というルールを決めておきましょう。どちらかのチーム全員がしっぽを取られる、または制限時間になったときに相手チームのしっぽをたくさん取っていたチームの勝ちです。「取りに行く」と「逃げる」の戦略性も加わり、ドキドキハラハラの遊び方が楽しめます。 - 「復活しっぽ」をめざせ!(4~5歳児向け)
保育士がつけた「復活のしっぽ」に触ると、しっぽを取られた子も復活できる、という遊び方です。子どもたちは普通のしっぽをつけて、スタートの合図と同時に普通のしっぽとりを行います。しっぽを取られたら、保育士がつけた「復活のしっぽ」を追いかけ、触ることができたら自分のしっぽが復活します。「復活のしっぽ」は「触るだけ」「取ったらダメ」というルールにして制限時間を設け、最後までしっぽを残していた子の勝ちとなります。「復活のしっぽ」をつける人数や制限時間で、全員が楽しめるよう調整しましょう。
「復活のしっぽ」はすずらんテープを細かく裂くなどして作り、ほかのしっぽと違った見た目にしても楽しめます。
この遊びのねらい
走る・よける・つかむといった全身運動を通して、敏捷性や持久力を養います。相手の動きを予測することで判断力や空間認知力が育ち、チーム戦では仲間との協力や応援を通して社会性も身につきます。勝ち負けを経験しながら、気持ちを切り替える力を育てることにもつながります。
長縄遊び「大波小波」

寒い季節の外遊びに人気の縄跳び。「大波小波」は歌に合わせて長縄を小さく、または大きく揺らし、跳ぶ人は歌詞のタイミングに合わせてジャンプするという遊びです。縄が止まっている状態から始めるので、長縄遊びが苦手な子にも参加しやすい遊びです。跳ぶほうも縄を回すほうも、タイミングを合わせる楽しさがあり、体を大きく動かす冬の外遊びにぴったりです。
対象年齢
4~5歳児
基本のルール
- 「おおなみこなみ ぐるっとまわって にゃんこのめ」という歌詞に合わせて遊ぶ。
- 長縄を回す子2人を決め、跳ぶ子は縄の近くに立つ。
- 「♪おーなみ こなみー」という歌に合わせ、回す子は縄を下のほうだけで左右に波のように揺らす。跳ぶ子はひっかからないように、縄を跳ぶ。
- 「♪ぐるっとまわって」で、縄を大きく回し、跳ぶ子はその場で跳び続ける。
- 「♪にゃんこのめ」の「め」のタイミングで、跳ぶ子は両足をパーに開いて縄をまたぐ。縄にひっかかったり、踏んだりせず、きれいにまたぐことができたら成功!
遊び方のバリエーション
- さざ波小波(3歳児向け)
縄を大きく回さず、縄の左右にジャンプを繰り返す遊び方です。歌もゆっくり歌いましょう。苦手な子や初めての子は、縄を置いたままの状態で行います。歌も「♪おおなみこなみ」を「♪さざなみこなみ」に、「♪ぐるっとまわって」を「♪ぐるっとまわさず」に変えてゆっくりと歌います。慣れたら、縄を地面に置いたままさざ波のように揺らし、その左右にジャンプして遊びます。最後は「♪にゃんこのめ」でピタッと縄をまたいでポーズ! - 2人同時にジャンプ!(4~5歳児向け)
中に入って跳ぶ人を2人に増やすやり方です。跳ぶほうも、回すほうもタイミングを合わせるのがより難しくなります。人数をどんどん増やしていくこともできますが、大人数になったら保育士が回してあげましょう。
この遊びのねらい
歌と縄の動きに合わせてジャンプすることで、リズム感や集中力を育みます。どのような歌か、どんな風に縄を回すのか、跳ぶのか、最初に保育士が見本を見せてあげると良いでしょう。足をそろえて跳んでいたところから、タイミングを合わせてパーに足を開いて立つ、という動作は、体幹やバランス力の向上につながります。また縄を回すほうも、回し続ける持久力や忍耐力、大きく縄を回す腕の力が養われます。
「跳ぶ」「回す」の交代の仕方のルールを自分たちで決めたり、友達がうまく挟めなかったときに「惜しい!」「ちょっと早かったよ!」などと声をかけたりする経験を通して、複数人で協力する外遊びならではの心の成長が見られます。
また、この縄跳び遊びの歌は、地域によって歌詞やリズムに違いが見られるようです。園の地域について調べてみたり、保護者に聞いてみたりするのも面白いかもしれません。
鬼ごっこ遊び「氷鬼」

「氷鬼(こおりおに)」は、鬼ごっこの一種で、オニにタッチされると体が「氷」になったように動けなくなる遊びです。タッチされるとオニが交代する鬼ごっこと違い、仲間に助けてもらうことで再び動けるようになるため、子ども同士で協力する楽しさも味わえます。ただ、オニは交代がない分、追いかけ続けることになるため、時間を決めてオニを交代するようにしましょう。鬼寒い冬でも体を思いきり動かせる遊びです。
対象年齢
3~5歳児
基本のルール
- オニが最初に10数えている間に、オニ以外の子は逃げる
- オニにつかまってタッチされた子は「氷」になり、動けなくなる
- 仲間がタッチしてくれると氷が溶けて動けるようになる
- 制限時間内で、全員が「氷」になったらオニの勝ち
- 制限時間がきたら、オニを交代する
遊び方のバリエーション
- 増える!氷鬼(4~5歳向け)
次のオニに交代するとき、オニを1人から2人に増やします。オニは氷になっている子から、じゃんけんで選びます。次の回が終わったら、今度はオニを2人から3人に増やします。オニが増えることでオニの負担は減り、オニ側も、逃げる側も状況をよく見て動くことがさらに必要になってきます。オニが増えると分かりづらくなるので、帽子などで区別しましょう。 - バナナ鬼(3~5歳児向け)
遊び方は氷鬼と同じですが、氷ではなくタッチされたらバナナになる「バナナ鬼」もあります。タッチされたら、バナナのように両手を頭の上で合わせてその場で止まります。仲間にタッチしてもらったら、両手を下げて(=バナナの皮がむける)また動くことができるようになります。
子どもたちと「タッチされたら何になる?」といろいろなアレンジを考えてみるもの楽しいかもしれませんね。 - 全員がハイハイの姿勢になり、オニを1人決める
- オニはハイハイで追いかけ、タッチされた子が次のオニになる
- 一定時間でオニを交代する
- 立ったり走ったりしてはいけない
- 保育士と1対1で楽しむやり方(0~1歳児向け)
ハイハイの動きが安定している子と、1対1で行いましょう。保育士がオニになり、ハイハイでゆっくり近づいて「つかまえた!」と優しく触れるだけでも、追いかけられるワクワク感を味わえます。 - 保育士と複数人数で楽しむやり方(2~5歳児向け)
保育士がオニになり、複数人数の子どもと行います。「ハイハイだけで移動する」というルールを理解し、「逃げる」「追いかける」のシンプルな遊びで全身運動を楽しみます。追いかけられるドキドキ感を全員が味わえるよう、保育士は緩急をつけたり、方向転換したりして、子どもたちを追いかけましょう。マットやクッションを置いて「トンネルくぐり」「山越え」にするなど、コースを工夫するとさらに盛り上がります。体幹やバランス感覚を養うのにも効果的です。 - クリスマス会や発表会で使う鈴やタンバリンなどの楽器を使い、「音に合わせてジャンプ遊び」などをすることで、季節行事と遊びを結びつけて楽しむ。
- 「雑巾がけ競争」「椅子運びリレー」のようにゲーム要素を取り入れた「大掃除」を取り入れる。遊びながら「年の終わりに身近な環境を整える」という習慣を体験し、達成感や自分も役割を担える喜びにつなげる。
- 家庭で過ごす時間が増える年末年始に向けて、「すごろく」や「かるた」などを園での活動に取り入れる。あらかじめ園で体験してルールを知っておくことで、親子で「やってみよう!」と楽しみやすくなる。
この遊びのねらい
氷になったり助けてもらったりする中で、子ども同士が自然に声をかけ合い、協力する姿が育ちます。追いかけたり逃げたりする全身運動は、持久力や俊敏性を養い、冬でも体をしっかり温められます。汗をかいたら着替えるなど、冬場の体調管理に気をつけましょう。オニも、氷を溶かすときも、タッチするときの強さに気をつけることを事前に伝えておきましょう。
室内でできる鬼ごっこ遊び「ハイハイ鬼ごっこ」
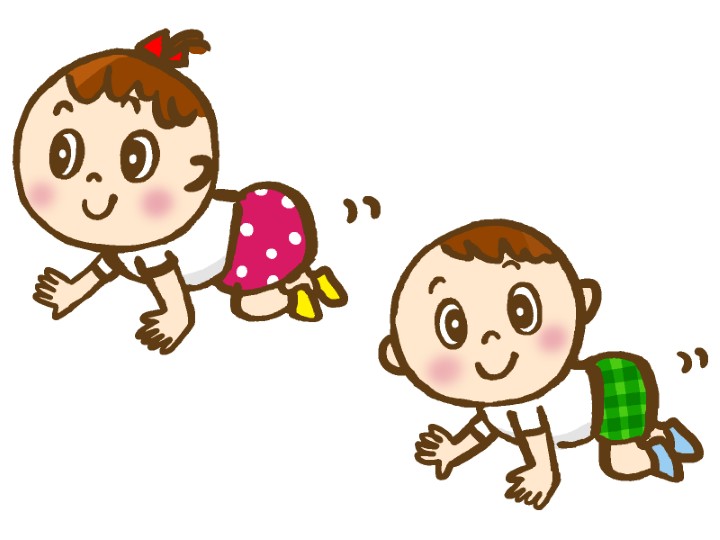
「ハイハイ鬼ごっこ」は、名前のとおり鬼ごっこを「ハイハイ」の姿勢で行う遊びです。走らずに遊べるため室内でも安全に楽しめ、全身を使って体を動かすことができます。もうハイハイをしない年齢の子どもたちにとっても、普段あまりしない姿勢での移動は、子どもにとって新鮮で笑い声が広がる遊びです。悪天候で戸外に出られないような日の室内遊びにおすすめです。
遊ぶ場所にマットを敷く、頭をぶつけそうなものは保護や撤去をするなどして、安全な環境を確保して行いましょう。
対象年齢
0~5歳児
基本のルール
この遊びのねらい
室内で各年齢で楽しめる遊びなので、屋外で遊べないときの運動不足解消にもつながります。ハイハイができるようになった低年齢児とは、目線を合わせてしっかりコミュニケーションを取りながら遊ぶことで、安心感・信頼感が育まれます。普段の生活ではもうハイハイをしない年齢の子どもたちにとっては、ハイハイの動作を通して、腕や足、体幹の筋力をバランス良く育てます。また、「相手(オニ)の動きを読む」「自分が動くスペースを判断する」という観察力、予測する力、判断力なども養われます。
子どもたちは夢中になってハイハイすると視野が狭くなるので、場所は広くとり、子ども同士の接触がないよう状況を見渡せる保育士を配置すると良いでしょう。
12月の遊びを充実させるヒント

12月の遊びを充実させ、子どもたちの満足感や成長を促す工夫をご紹介します。
「元気に外へ」「寒さに親しむ」をキーワードに冬を楽しむ
寒さが厳しくなる12月ですが、子どもたちが思いきり体を動かす外遊びは、冬こそ大切にしたい活動です。鬼ごっこや長縄など、友達と関わりながら、全身が温まるよう遊びを取り入れて、寒さに負けない体づくりにつなげましょう。
行事やイベントの多い12月は、体調管理がいつも以上に気になるところです。元気に遊んで汗をかいかたら、汗をふく、着替えさせるなどのこまめな対応を行うことも大切です。
1日の中で思い切り体を動かす時間を作ることでメリハリを生み、バランス良く活動することを目指しましょう。
12月の遊びをより豊かにする+αのアイデア
ひと工夫することで、子どもの「楽しかった!」や「またやりたい!」を引き出しましょう。
まとめ
12月は園の行事も多く、年末に向けて何かと生活が慌ただしくなりがちです。子どもたちも園行事の準備などに時間を使うことが増えますが、室内や屋内の遊びを取り混ぜて、体を動かす時間を意識的に設け、生活のメリハリをつけて過ごしましょう。体と心の成長を注意深く見つめながら、遊びを通して子どもたちの創造力や感情表現を豊かにしていきたいですね。