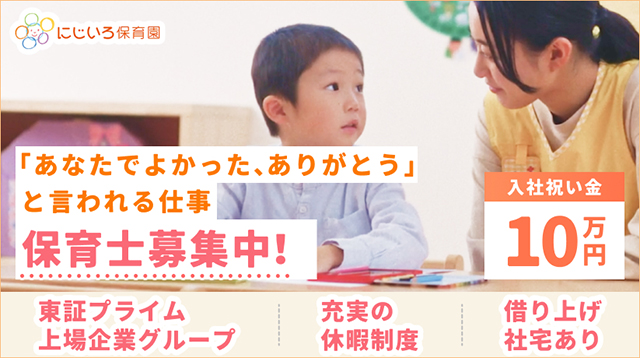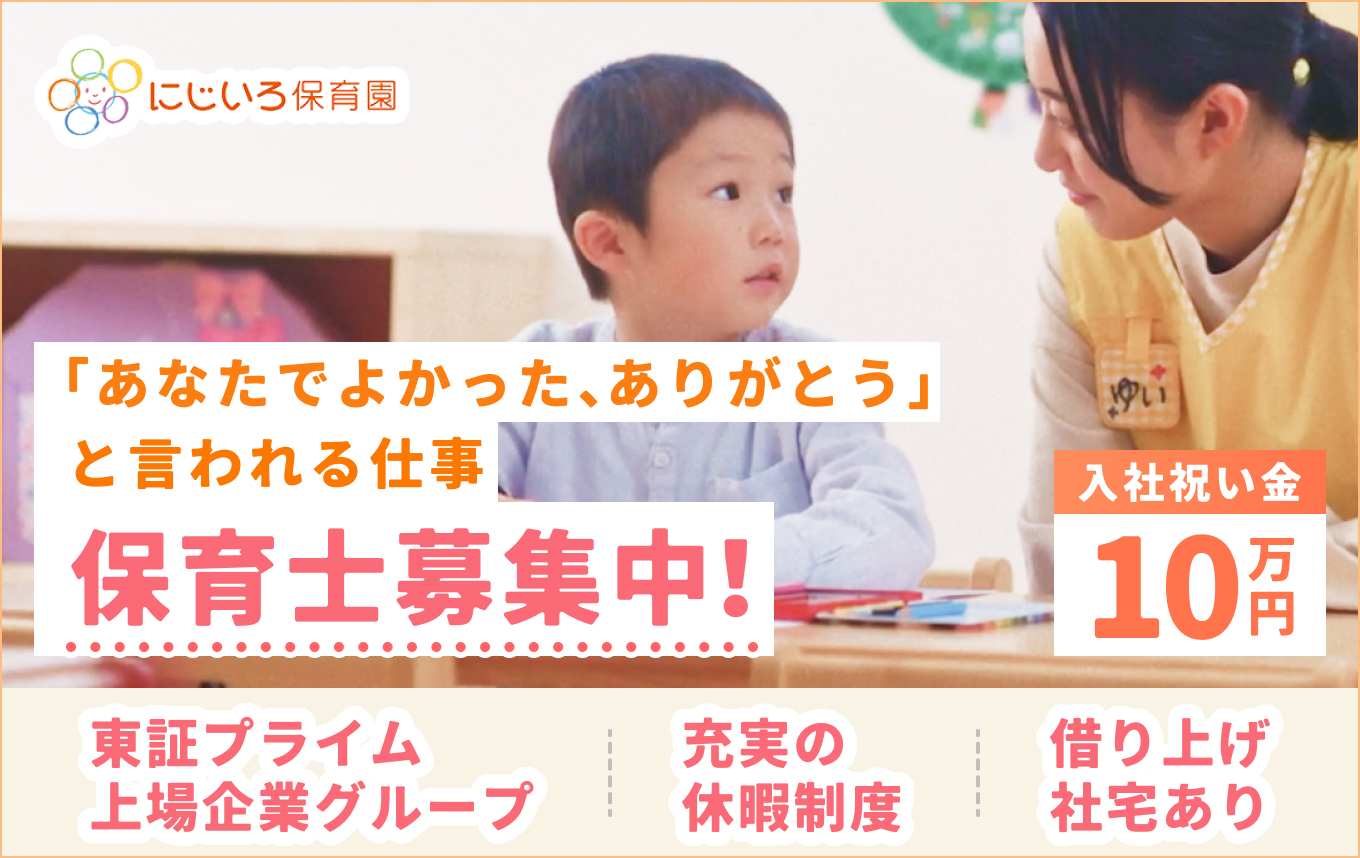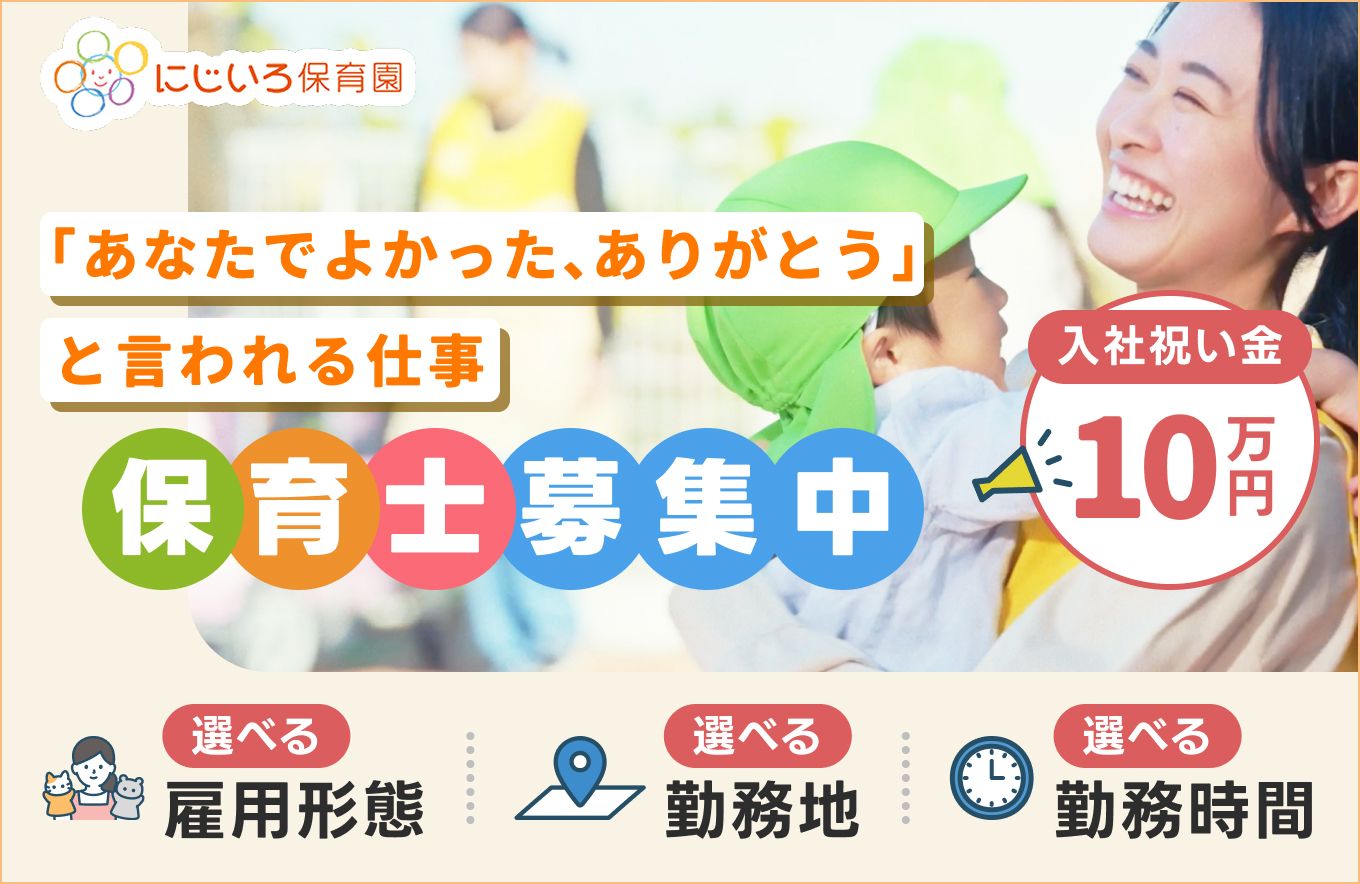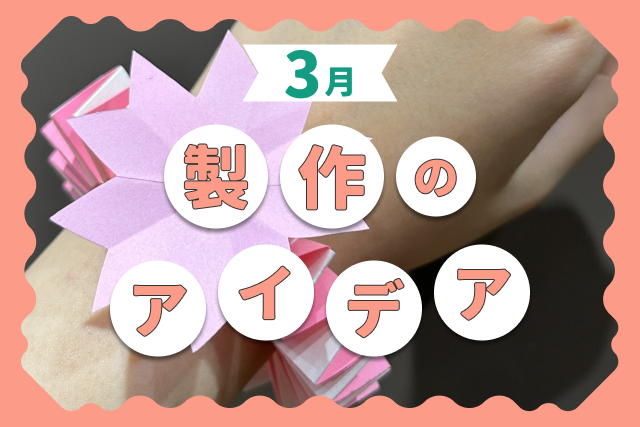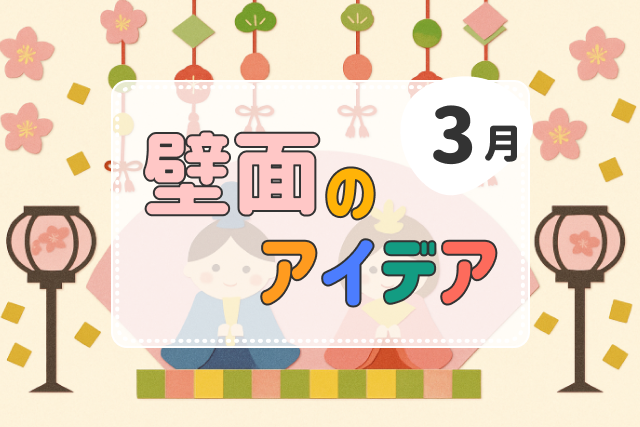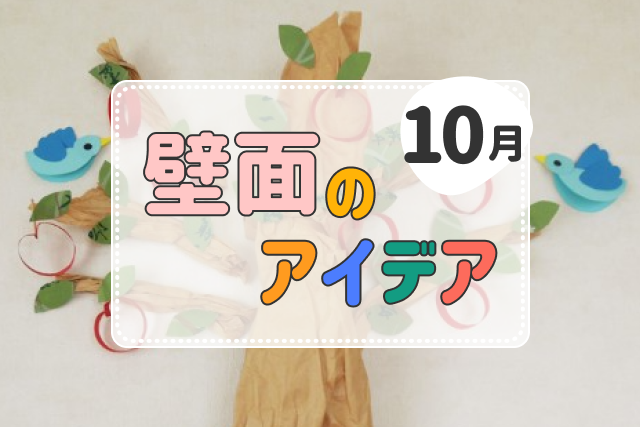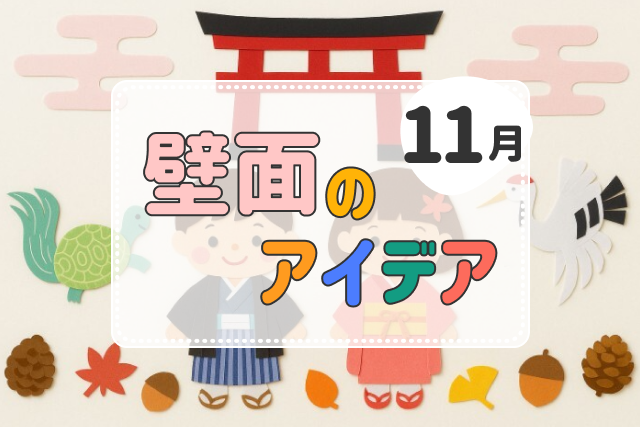2025.07.25
保育実習生必見!名札作りのコツとおすすめ素材
保育実習において、名札は子どもたちとの距離を縮める大切なコミュニケーションツールです。「どんな名札を作ればいいの?」「手作りって難しそう…」そんな不安を抱える実習生に向けて、この記事では名札作りの前に確認しておきたいことや作り方のポイント、初級者向けから上級者向けまでの具体的な作り方例などをご紹介します。
なぜ名札が大切?実習での役割とは
実習の名札は子どもたちから名前を憶えてもらうきっかけになり、文字が読めない子どもたちからも、モチーフで視覚的に覚えてもらう助けになります。子どもたちは「〇〇せんせい!」と名前で呼びかけることで親しみを感じ、距離がぐっと縮まります。
また、名札があることでほかの保育士や保護者からも、実習生として把握してもらいやすくなり、挨拶やコミュニケーションを円滑に行うことができます。
実習先のルールをチェック!名札作りの事前確認ポイント

園によってルールや指定があるときは、それに沿った名札を準備するのが原則です。事前に確認しておきたいポイントは次の5つです。
キャラクターや派手なデザインはOK?
人気のキャラクターをデザインした名札は、親しみをもってもらいやすいメリットがありますが、園によってはキャラクターを使うことをNGとしていることがあります。その場合は、キャラクター全般が禁止なのか、特定のキャラクターが禁止なのか、事前に確認しておきましょう。また金や銀など、光る色味を多用した派手なデザインは避けた方が無難です。
名前はフルネーム?下の名前だけ?
「〇〇せんせい」と呼びやすいように、下の名前だけで作ることが多いですが、フルネーム指定の園もあります。漢字教育をすすめている園もあるので、表記が漢字かひらがなかも含めて園の方針をチェックしておきましょう。
安全ピンは使っても大丈夫?代替方法は?
針のある安全ピンは、子どもとのふれあいで思わぬ事故につながることがあるため、名札での使用を禁止している園も少なくありません。その場合は、面ファスナーなどの代替方法についても指定があるか、しっかり確認しておきましょう。
名札の大きさ・素材に指定はある?
「〇cm角まで」「フェルトや布で」など、素材やサイズを指定されることがあります。市販のプラスチックの四角い名札は、角が子どもに当たると危険なため、おすすめしません。また、ビーズやスパンコールなどを名札の飾りに使うのは、万一取れたときに誤飲の危険があります。
名札はいつ・どこに付ける?
一般的には、実習の際に着用するエプロンの胸元に、常時付けることが多いようですが、園によっては、子どもが見やすいようにエプロンの下側にあるポケットの位置に付けることもあります。作った名札が付けにくくないか、実習で着用予定のエプロンなどで事前にチェックしておくと安心です。
名札作りの基本をおさえよう!デザイン・素材・取り付けの工夫
せっかく手作りするなら、子どもに親しまれるデザインの名札にしたいですよね。そして実習で使う名札を作るためには、「扱いやすさ」「安全性」「見やすさ」を備えていることが必要です。名札作りを始める前に、おさえておきたいポイントを解説します。
名札の大きさの目安:見やすく、扱いやすいサイズで
名札の大きさは、目立ちすぎず、でも子どもたちがしっかり見える大きさが理想です。目安としては、「縦5〜7cm×横8〜10cm」程度の長方形や丸型が扱いやすいです。大きすぎると活動の妨げになることもあるので、注意しましょう。
名札のデザインの決め方:親しみやすさを意識
名札のデザインは、子どもにとって親しみやすく、わかりやすいものを選ぶことが大切です。名前が見やすい配置になっているか、色の組み合わせに違和感がないかも確認しましょう。キャラクターや動物、果物など、子どもが好きなモチーフを選ぶのがおすすめです。また、自分の好きなものを名札のモチーフにしても、「先生はこれが好きなんだよ」とコミュニケーションのきっかけにもなります。以下のようなモチーフは、保育現場でもよく使われています。
動物
くま・うさぎ・いぬ・ねこ・パンダなど、かわいらしく覚えやすい動物は人気です。
花
ひまわり・チューリップ・さくら・コスモスなど、季節感を取り入れることもできます。
食べ物
いちご・りんご・ぶどう・スイカなどは、子どもが親しみやすく、色合いも鮮やかです。
キャラクター
キャラクターの使用がOKな保育園であれば、ディズニーやジブリのキャラクターや、アニメの「アンパンマン」「ミニオンズ」、人気絵本の「はらぺこあおむし」などもおすすめです。キャラクターをデザインに使う場合は、子どもの興味が集中しすぎないよう、大きさにも気を付けましょう。
その他
星・ハート・虹・雲・音符など、やさしい印象を与える抽象的なモチーフも人気です。
名前の見せ方の工夫:ひらがな&はっきりが基本
名前は視認性に配慮して、「太く・はっきり・ひらがな」で書くのが基本です。読みやすいフォントや色づかいに気を配り、装飾に埋もれないよう名前をしっかり目立たせることが大切です。刺繍やアイロンプリントなどの方法を使えば、よりくっきりとした仕上がりになります。
取り付け方法の工夫:何よりも安全を重視
安全ピン以外の方法としては、「面ファスナー」「クリップ」「スナップボタン」などがおすすめです。子どもが触っても危険がなく、簡単に外れないことがポイントです。より安全性の高い取り付け方を意識しましょう。
安全ピンの使用が許可されている場合でも、針が飛び出しにくいロック式の安全ピンや、カバー付きの製品を選ぶと安心です。
名札に適した素材選び:フェルト・布・市販アイテムを活用
名札に最も使いやすい素材はフェルトです。柔らかくて針通りが良く、初心者でも扱いやすいのが魅力。カラー展開も豊富なので、「乳児向けのやさしい色」「幼児向けの明るい色」など、対象年齢に合わせた色選びも楽しめます。刺繍などの装飾も加えやすく、オリジナリティを出すのにぴったりです。フェルト以外の布を使う場合は、チェック・ドットなど布の柄を活かしたデザインにすることもできます。
また、手芸店や100円ショップ、通販サイトなどで購入できる市販のワッペンなどを活用すると、裁縫が苦手な方でも手軽に作ることができます。好みや技術に合わせて、素材の組み合わせを工夫しましょう。
作る前のひと工夫:材料とデザインを紙に書き出してみよう
頭の中でなんとなくイメージを描くだけでなく、名札に使いたい材料や色、入れたいモチーフや文字の配置を紙に書き出しておくと、実際の制作がぐっとスムーズになります。特に手作りに不慣れな方は、ラフスケッチを描くことでバランスや工程をイメージしましょう。準備段階でのひと工夫が、完成度の高い名札につながります。
裁縫が苦手でも大丈夫!簡単な作り方のコツ
「裁縫が苦手…」という方から、「オリジナリティある名札に挑戦したい!」という上級者まで、実力に合わせて作れる名札の作り方を紹介します。
初心者さんも安心!針と糸を使わないラクラク名札

アイロン接着フェルトとひらがなワッペンを使った、シンプルで作りやすい名札の作り方をご紹介します。針と糸を使わなくても、手軽にしっかり仕上がるので、裁縫が苦手な方にもおすすめです。
材料
型紙/アイロン接着フェルト/アイロン接着ひらがなワッペン
道具
チャコペン/ハサミ/アイロン
作り方
- デザインに合わせた型紙を作る。
- フェルトに型紙を乗せ、チャコペンでなぞる。
- チャコペンの線に沿って、土台やパーツのフェルトをハサミで切る。
- 土台となるフェルトにパーツのフェルトをアイロンで接着する。
- アイロンでひらがなワッペンを接着する。
ポイント
- 名札の土台になるフェルトは、同じものを2枚重ねると補強になります。
- 普通のフェルトを布用接着剤で貼り付けて作ることもできます。
- アイロンで貼り付けたあと、フェルトが冷めてから次のパーツを貼るようにすると、きれいに仕上げやすくなります。
- ひらがなワッペンの代わりに、ゼッケン用の布(100円ショップなどにあるアイロン接着できるもの)に名前を書いて貼り付けても。
少しステップアップ!手縫いで仕上げる中級者向け名札

「少しだけ凝った名札にチャレンジしてみたい」「針と糸を使って温かみのある仕上がりにしたい」という方には、手縫いで仕立てる名札がおすすめです。
材料
型紙/フェルト/刺繍糸/糸
道具
チャコペン/ハサミ/針
作り方
- デザインに合わせた型紙を作る。
- フェルトに型紙を乗せ、チャコペンでなぞる。
- チャコペンの線に沿って、土台やパーツのフェルトをハサミで切る。(土台は2枚用意する)
- 土台となるフェルトの1枚に、パーツのフェルトを刺繍糸や縫い糸で縫い付ける。
- パーツを縫い付けた土台のフェルトに、もう1枚にフェルトを縫い合わせる。
ポイント
- 名前の部分は、ひらがなワッペンのほか、フェルトを切って縫い付けても。
- 刺繍糸の色をデザインのアクセントにすることもできます。
- 土台のフェルト2枚を縫い合わせるときに、中に綿を入れるとぷっくりと可愛い、立体的な名札に。
こだわりの一点を丁寧に!刺繍で仕上げる上級者向け名札

「裁縫が好き!」という方は、デザインにアップリケや刺繍を取り入れた名札に挑戦してみませんか?細やかなステッチやパーツ配置にこだわれば、子どもたちの印象にも残る、オリジナリティにあふれた名札になります。
材料
型紙/フェルト/刺繍糸/糸
道具
チャコペン/ハサミ/針
作り方
- デザインに合わせた型紙を作る。
- フェルトに型紙を乗せ、チャコペンでなぞる。
- チャコペンの線に沿って、土台やパーツのフェルトをハサミで切る。(土台は2枚用意する)
- 土台となるフェルトの1枚に、名前の枠用のフェルトを貼り付ける
- 名前の枠を囲むように刺繍糸で模様を刺し、フェルトのパーツを縫い付ける。
- 名前を刺繍する。
- パーツを縫い付けた土台のフェルトに、もう1枚にフェルトを縫い合わせる。
ポイント
- 名前の部分は、ミシン刺繍にしても良いでしょう。
- 細かいパーツは取れないよう、布用接着剤で貼ってから縫い付けるとさらに安心です。
完成した名札には、園の指定などに沿って、名札の裏側や上部に安全ピンやクリップを取り付けましょう。面ファスナーの場合はアイロンで付けられるものを使うと簡単です。
毎日付けていると、名札が汚れたり、壊れてしまったりすることもあります。予備の名札を作っておくと、いざというときに安心ですよ。
まとめ
子どもたちと「はじめまして」のとき、コミュニケーションのきっかけになってくれる名札。「どんな名札にしよう?」と考える時間は、自分が保育の現場に立つ準備でもあり、子どもたちとの出会いを想像する楽しいひとときにもなるはずです。
大切なのは、見た目の完成度よりも「安心して関わってほしい」「名前を覚えてもらえたらうれしい」という気持ち。自分らしい名札で、実習の第一歩を踏み出しましょう。
事前に実習先の園を訪問する機会があれば、先輩保育士たちの名札や付け方を見て、参考にしましょう。
ライクキッズが首都圏を中心に150園以上運営している「にじいろ保育園」では、園見学を受け付けています。保育の現場を実際に見て、働くイメージをふくらませてみませんか?