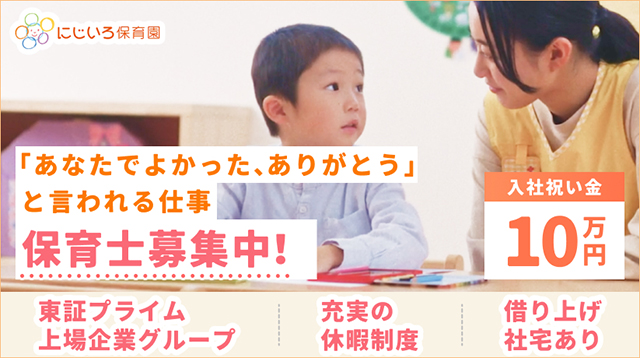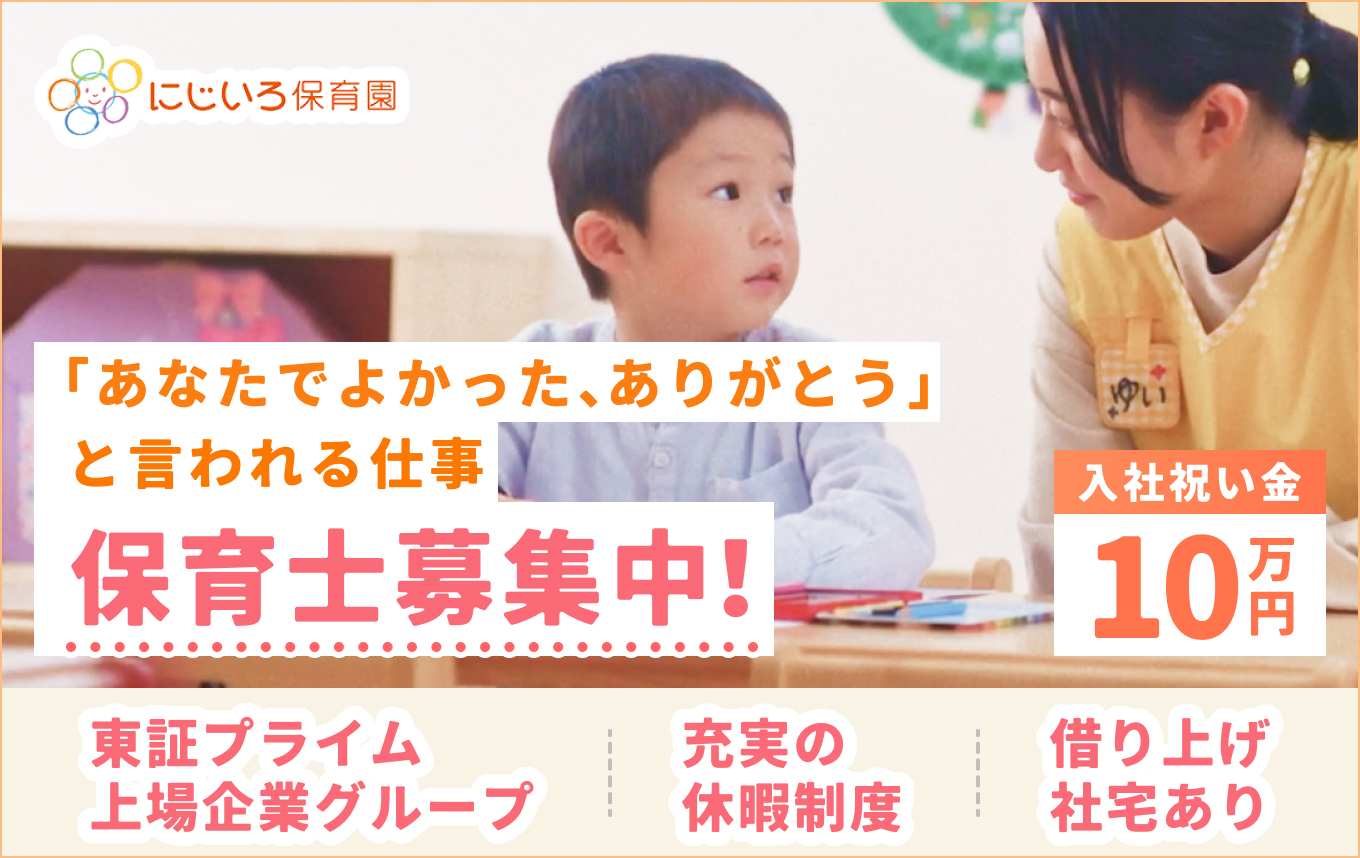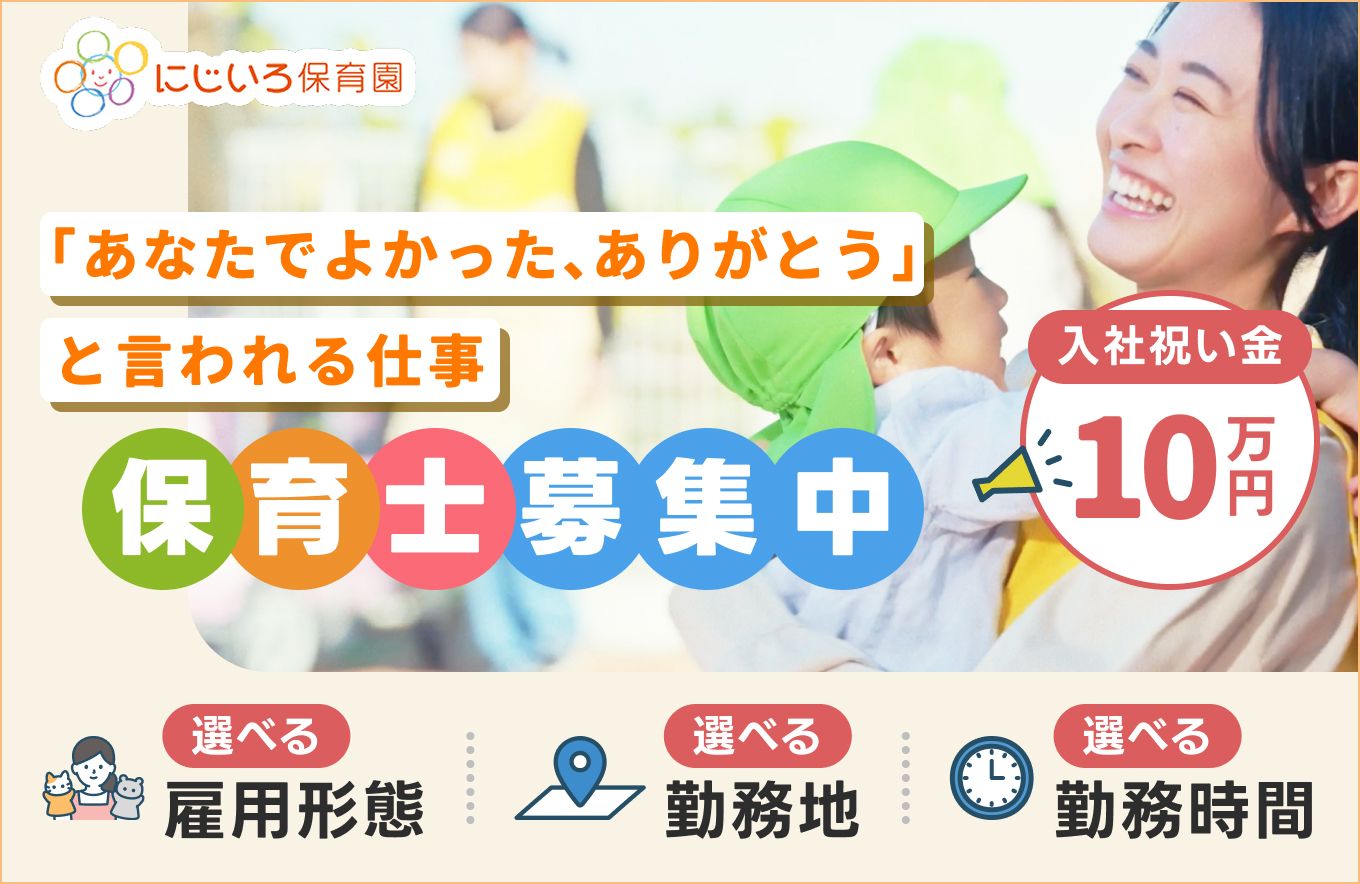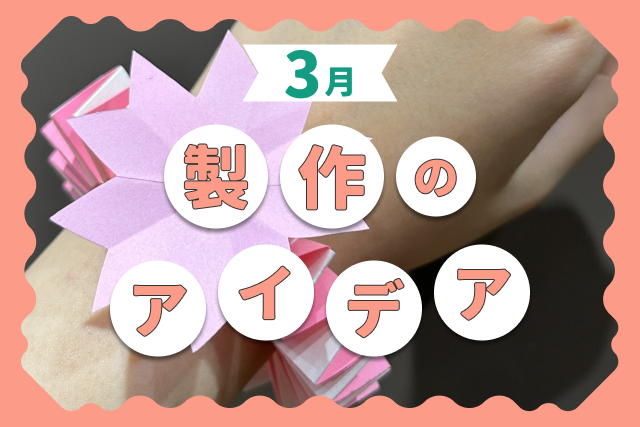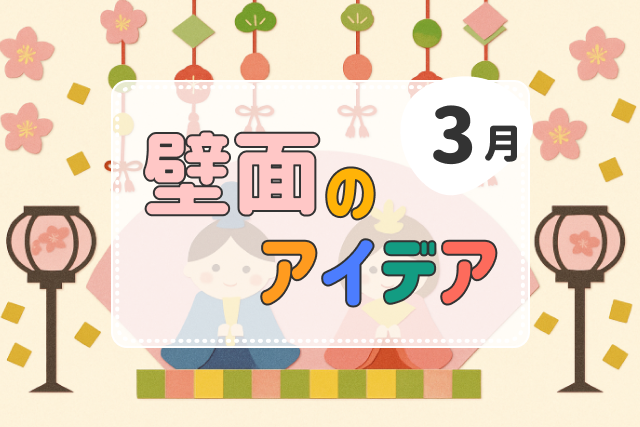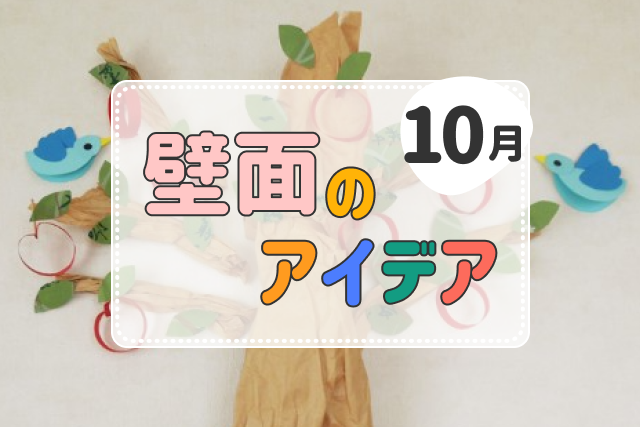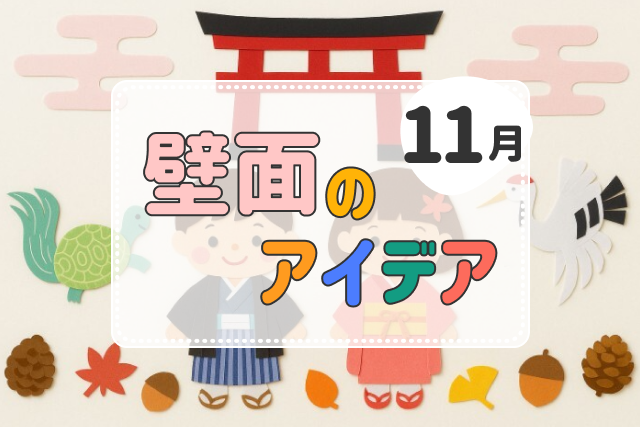2025.07.28
実習日誌の書き方完全マスター|項目別のポイントと注意点
保育実習日誌(以下、実習日誌)は、単なる実習の記録ではなく、自分の学びや成長を形にする大切なツールです。その日の実習を振り返りながら書くことで、子どもへの理解が深まり、保育士としての視点も身についていきます。本記事では、項目ごとの書き方、注意点や書くコツまで、初めての実習で役立つポイントをわかりやすく解説します。
実習日誌とは?各項目の書き方のポイント&記入例

実習日誌には、毎日の活動や気づきを記録するための項目が設けられています。書き方に正解はありませんが、大切なのは「子ども」「保育士」「実習生」の3つの視点を意識すること。それぞれの関わりの中で何が起こっていたかを観察し、自分の言葉で記録していくことが成長につながります。
園によってフォーマットは異なりますが、ここでは一般的な実習日誌における項目ごとの書き方のコツと具体的な記入例をご紹介します。
基本情報:日付・天気・担当クラスなど
実習日誌の冒頭に記載する基本情報です。担当クラスの年齢、人数などを正確に記録して、把握しておきましょう。
書き方ポイント
園の許可があれば、当日の朝や休憩時間などの記入できるタイミングで書きましょう。
記入例
「9月10日(火)/晴れ/うさぎぐみ(3歳児)/担任:佐藤先生/男児9人・女児11人」
1日の目標・ねらい
その日の保育を通じて、どのようなことを意識して子どもに関わるかを示す項目です。
書き方ポイント
- 気負いすぎず、「1日の保育の流れを把握する」といったシンプルなものから始めましょう。
- クラスの年齢や発達段階によって、活動や学びたい目標が変わることを意識します。
- 園の保育計画や、下記のような公的資料には、保育を通して育みたい力やそのために必要な保育内容がまとめられています。参考にすると良いでしょう。
記入例
「~を学ぶ」「~を観察する」「~を意識する」「~を理解する」のような結びで書くと、目標が明確になります。
<0~1歳児>
「食事の介助を通して、子どもの咀しゃくや飲み込みの発達に合わせた援助方法を学ぶ」
「午睡時の保育士の関わり方を観察し、子どもが安心して眠れる環境づくりを知る」
「自由遊びの中で、はいはいや伝い歩きの子どもに対する安全な見守り方を学ぶ」
<2~3歳児>
「排泄の援助を通して、自立に向けた声かけやタイミングの取り方を学ぶ」
「絵本の読み聞かせ時に保育士の姿勢や声のトーンを観察し、子どもの集中を促す工夫を知る」
「室内遊びの中で起きたトラブルに対して、保育士がどのように仲裁しているかを学ぶ」
<4~5歳児>
「製作活動の中で、保育士が子どもの創造力を引き出す支援の仕方を観察する」
「集団遊びの場面で、子ども同士のやりとりや協力の姿を見て、社会性の発達を理解する」
「戸外活動におけるルールや危険の伝え方について、保育士の援助方法を学ぶ」
活動の時間と内容
1日の流れを客観的に記録するための大切な項目です。保育現場では、子どもたちの生活リズムに沿った時系列の保育活動が行われています。
書き方ポイント
- 時刻と活動内容をセットで簡潔に書くのが基本です。
- 活動の合間にこまめなメモを取っておくと、実習後の記録がスムーズになります。
記入例
「8:00 登園」
「9:30 朝の会」
「10:00 お絵かき」
「11:30 給食」
「12:30 午睡」
「15:00 おやつ」
「15:30 外遊び」
「16:30 順次降園」
環境構成
「環境構成」は、子どもが活動に参加しやすく、安全に過ごせるように整えられた保育環境の工夫や準備を記録する項目です。保育士がどんな意図をもって準備・配置を行っているのかを観察しながら記録することで、「子どもが安心して過ごせる空間づくり」の学びにつながります。
書き方ポイント
- 文章や図を使って、机や椅子の配置、道具の置き方、保育士の位置などを具体的に記述しましょう。
- 子どもの動線や集中しやすさ、保育士の意図が感じられるポイントを捉えることが大切です。
- 図はフリーハンドではなく、定規などを使って見やすく書きましょう。
記入例
(朝の会)「子どもたちの椅子を半円形に並べ、保育士は前方中央に立つ」
(製作)「机を2つずつ向かい合わせに配置。製作に使う廃材を段ボールの中に用意しておく」
(午睡)「布団を敷き、電気を消す。起きた子どもが静かに遊べる玩具を用意する」
子どもの様子
「子どもの様子」は、活動中や日常生活の中で子どもがどのように行動し、反応していたかを観察し、記録する項目です。子どもの「行動の理由」や「感情の変化」への気づきを深め、保育士に必要な観察力を高めることにつながります。
書き方ポイント
- 「楽しそうだった」「元気だった」といった単発な印象ではなく、観察した具体的な活動内容を記述しましょう。
- クラス全体の様子や個人の様子、両方を意識して観察し、気づいたことを記入します。
- 複数の子どもを観察する場合は、年齢差・性格・関係性などにも着目して違いを書くと◎。
記入例
(朝の会)「椅子に座り、名前を呼ばれたら返事をする。途中で歩き回る子どももいた」
(給食)「当番の子どもが前に出て『いただきます』の挨拶をする」
(外遊び)「園庭では砂遊びが人気。協力してトンネルを掘っている子どもたちもいた」
保育者の動き・配慮
この項目では、保育士が子どもにどのように関わっていたか、活動をどのように支えていたかを記録します。保育者の行動・言葉・表情・配置など、子どもの安全や成長を支えるための工夫や配慮に注目し、実習生が「学びになった」「気づきがあった」と感じた場面を具体的に書きましょう。
書き方ポイント
- 活動中や場面ごとの「保育者の行動・声かけ」に注目して観察しましょう。
- 単に「優しかった」「見守っていた」といった感想で終わらず、具体的な動き・言葉を含めるように意識します。
- 「なぜそのように関わっていたのか?」を簡潔に補足すると、より深い記録になります。
記入例
(登園)「子どもの目を見て名前を呼び、『おはよう』と笑顔で声をかける。保護者に家庭での様子や体調について聞く」
(製作)「最初に見本を見せながら工程を説明する。危険防止のため、はさみは使う直前に配る」
(自由遊び)「転倒などの危険を防ぐため、また遊ぶスペースを広くとるために、誰も遊んでいない玩具は片付けていた」
実習生の気付き
「実習生の気付き」は、実習中に観察したことや経験したことから得られた学びや発見を、自分の言葉で記録する項目です。子どもや保育士の関わりを見て「なるほど」と感じたこと、思っていた保育との違い、自分の行動をふり返って気づいた点などを、素直に具体的に書き出しましょう。
書き方ポイント
- 「~だった」と感じた理由や背景まで考えて書くと、より深みのある記録に。
- 保育者の動きや子どもの姿を見て学んだことを中心に、自分の視点で表現しましょう。
- 一つの出来事から複数の気づきが得られることもあるので、印象に残った場面に焦点を絞ると書きやすいです。
記入例
(朝の会)「名前を呼ばれて返事ができない子どもがいたが、保育士はその子のペースを受け止め、決して急かさず見守っていた。小さな声でも返事ができたときは、子どももうれしそうな表情をしており、寄り添う姿勢を見習いたいと思った」
(散歩)「立ち止まる子どもがいたら、子どもが何に目を向けているかを確認し、興味を持ったものについて『きれいなお花だね』などと一度共感してから、歩くことを促していた。子どもが見ている世界を大事にしながら関わることが、信頼関係を築く第一歩になるのだと感じた」
(製作)「子どもによって進め方や表現方法が異なっていて、同じ説明でも受け取り方が違うことを実感した。保育者が一人ひとりに合わせた声かけをしていたことも印象に残り、『みんな同じ』でなくていいことにあらためて気づかされた。私も子どもに合った関わり方を意識していきたい」
1日の感想・反省・課題
1日の保育実習を終えて、自分が感じたこと・できたこと・うまくいかなかったこと・今後への課題などをふり返り、まとめるための項目です。活動ごとの細かなふり返りではなく、「その日の目標に対してどうだったか」「実習を通してどんな学びがあったか」を広い視点で考察します。
書き方ポイント
- 事実→気づき→感想・今後の順で整理すると読みやすくなります。
- できなかったことや戸惑ったことも、正直にふり返ることで成長の材料になります。
- 疑問に思ったことや、次に取り組みたいことも積極的に書きましょう。
記入例
「朝、泣いている子への声かけに迷い、気持ちをどう受け止めれば良いかわからなかった。保育士が『〇〇ちゃん、寂しいんだね』『今日は〇〇で遊ぼうか』と室内に意識が向くように優しく声をかけると、子どもが次第に落ち着いていった様子が印象的だった。私も子どもの気持ちに寄り添う対応を心がけたい」
「昨日までと比べて急に気温が上がり、保育士がこまめに子どもたちの様子を観察し、水分補給や服装の調節に目を配っていました。暑さに体が慣れていない子どもたちが多い中、早めに対策をすることの大切さを学びました」
「1日を通して、保育士が常に子どもの目線で話しかけていたことが印象に残った。私も立ったまま話すのではなく、なるべくしゃがんで目線を合わせることを意識したい」
書くときに気をつけたい3つのこと

実習日誌は、自分の学びを記録し、ふり返るための大切なツールです。書く内容だけでなく、「どう書くか」も実習の一部。読み手である保育士にも伝わりやすいよう、以下の3つのポイントを意識して書きましょう。
(1)読みやすい文字を書く
保育現場では、多くの人が実習日誌に目を通します。文字に自信がなくても、丁寧に書くことを心がけましょう。どんなに内容が良くても、文字が読みにくいと伝わりません。とくに数字・漢字・送り仮名は崩れやすいため注意が必要です。
時間がなくて焦って書くときもあるかもしれませんが、「行間を広めに取る」「一文ごとに少しペンを止める」などの工夫も効果的です。
(2)丁寧な言葉づかいと見直し
実習日誌は、自分自身の実習の記録であるとともに、園や学校に提出する書類でもあります。誤字・脱字がないか、記入もれがないか見直す習慣をつけましょう。
書く内容は、「です・ます調」または「だ・である調」のどちらかに統一します。(反省は「です・ます調」、表は「だ・である調」で分けることは問題ありません)
話し言葉ではなく、書き言葉を用いることに注意し、「ら抜き言葉」や「い抜き言葉」も避けましょう。
(例)
「~を見ました」→「~を観察しました」
「食べれました」→「食べられました」
「見てました」→「見ていました」
書き終えたあとに声に出して読んだり、1文ずつゆっくり見直したりすることで、口語的な表現に気づきやすくなります。
保育用語を適切に使おう
実習中は、初めて出会う保育用語も多いかもしれません、日誌の中でもできる範囲で積極的に使ってみましょう。意味が曖昧な言葉は調べたり、保育士に確認したりしながら、使い慣れていくことが大切です。
(例)
「午睡」→「お昼寝」
「おしっこ・うんち」→「排尿・排便」
「子どもに~させる」→「促す」「声かけをする」「援助する」
スラスラ書ける!実習日誌が負担にならない工夫

実習が終わってから日誌に取りかかると、「何を書けばいいか思い出せない」「疲れてなかなか進まない」と悩むことも多いはず。でも、少しの工夫で「書きやすさ」はぐっと上がります。ここでは、実習日誌をスムーズに書くためのコツを3つご紹介します。
(1)忘れないうちに!こまめなメモで内容を確保
保育の現場では、1日にさまざまな出来事が起こるため、実習後に記憶だけで書くのは大変です。活動ごとや、気づいたときに短くて良いのでメモを取る習慣をつけておきましょう。(例:「Aちゃん、お着替えで泣く→保育士が歌で声かけ」)「子どもが話していた言葉」「保育士の声かけの言い回し」など、細かな出来事のメモが役立ちます。
また、実習の休憩時間にそのメモを整理したり、メモをもとに実習日誌の記入を進めたりしておくと、実習後の負担が軽くなります。しかし、「休憩時間はきちんと休憩を取ってほしい」と考えている園もありますので、休憩時間に日誌を書いて良いか、あらかじめ確認するようにしましょう。
(2)書くことを意識して実習にのぞむ
「あとで日誌に書くとしたら、どんな場面を残したいか?」という視点で実習に参加すると、自然と観察のアンテナが立ちます。
【子どもの様子】
→ 保育士の声かけにどんな反応をしていたか?
→ 活動中、積極的な子・控えめな子の違いは?
【保育者の動き】
→ 製作でどんな道具をどこに配置していたか?
→ 個別対応のとき、どんな言葉で安心させていたか?
こうした「書くことを意識した観察」が、実習日誌だけでなく、自身の保育力の向上にもつながります。
(3)振り返りを次に活かす!目標につなげる考え方
実習日誌は「書いたら終わり」ではありません。今日の振り返りから、次の日の目標につなげることが、より実践的な学びになります。
「泣いていた子への対応に戸惑った」
→「明日は保育士の声かけを意識して観察しよう」
「子どもとの距離感がつかめなかった」
→「次は目線を合わせて話しかけてみたい」
1日の経験をそのまま終わらせず、「次にどう活かすか」を考えることで、日誌が単なる記録ではなく「自分を育てるノート」になります。
まとめ
実習日誌は、できたことだけでなく、できなかったことや悩んだことも含めて、自分の成長を記録する大切なツールです。慣れないうちは書くのに時間がかかり、負担に思うこともあるかもしれませんが、日々の経験を丁寧にふり返ることで、「子どもがなぜそう動いたのか」「保育士がなぜそのように対応したのか」といった「保育の背景」が少しずつ見えてくるようになります。自分の気づきや学びを言葉にしていくことで、実習の効果を最大限に活かしてくれる実習日誌は、将来保育士になったときもきっと役立ってくれることでしょう。
事前に実習先の園を訪問する機会があれば、園内や保育活動の様子を見学させてもらい、実習のときに目を配るポイントの参考にするのも良いでしょう。
ライクキッズが首都圏を中心に150園以上運営している「にじいろ保育園」では、園見学を受け付けています。保育の現場を実際に見て、働くイメージをふくらませてみませんか?