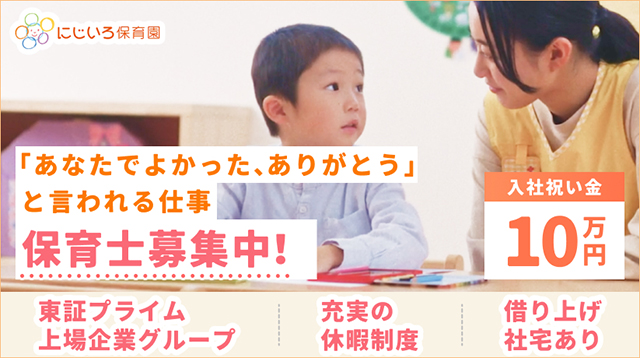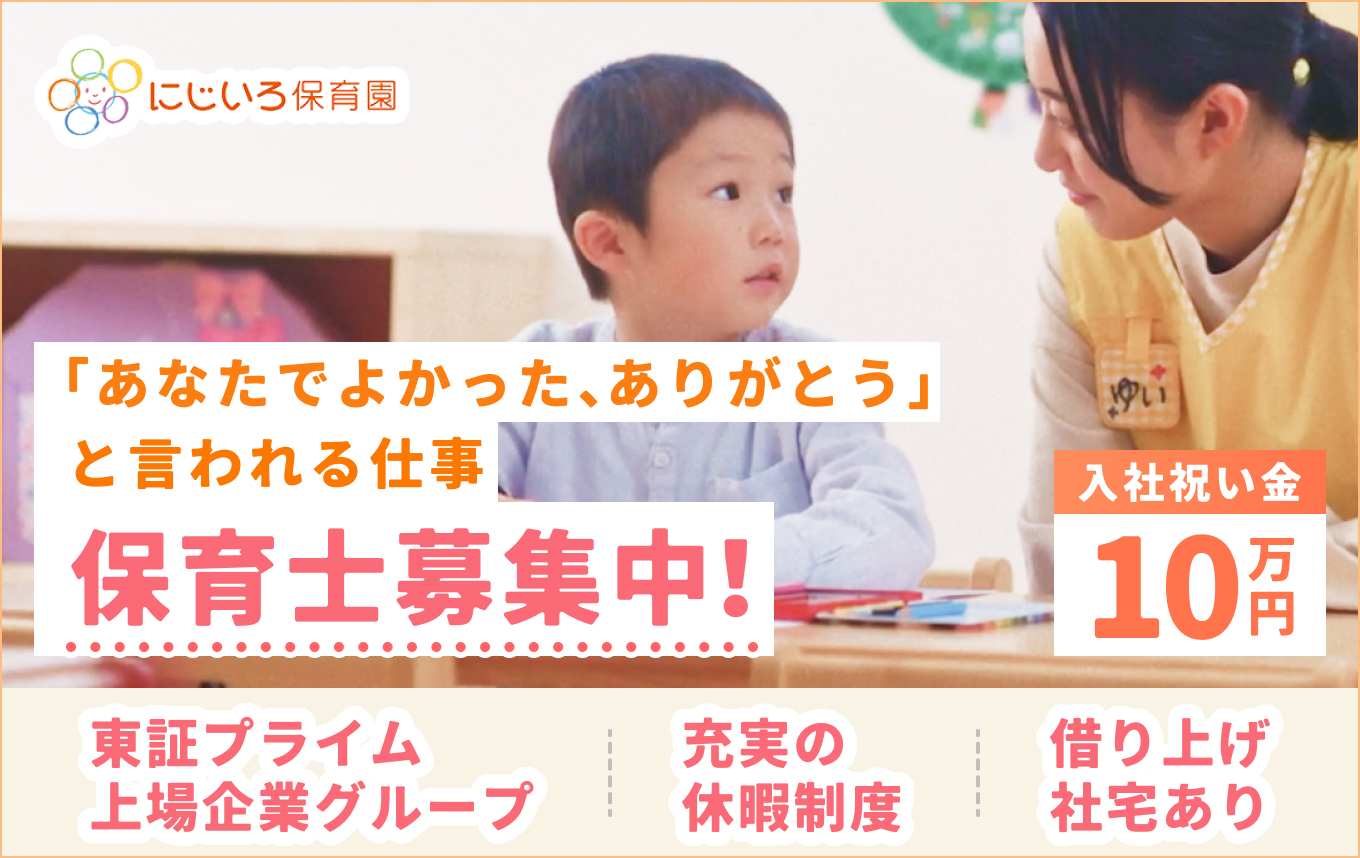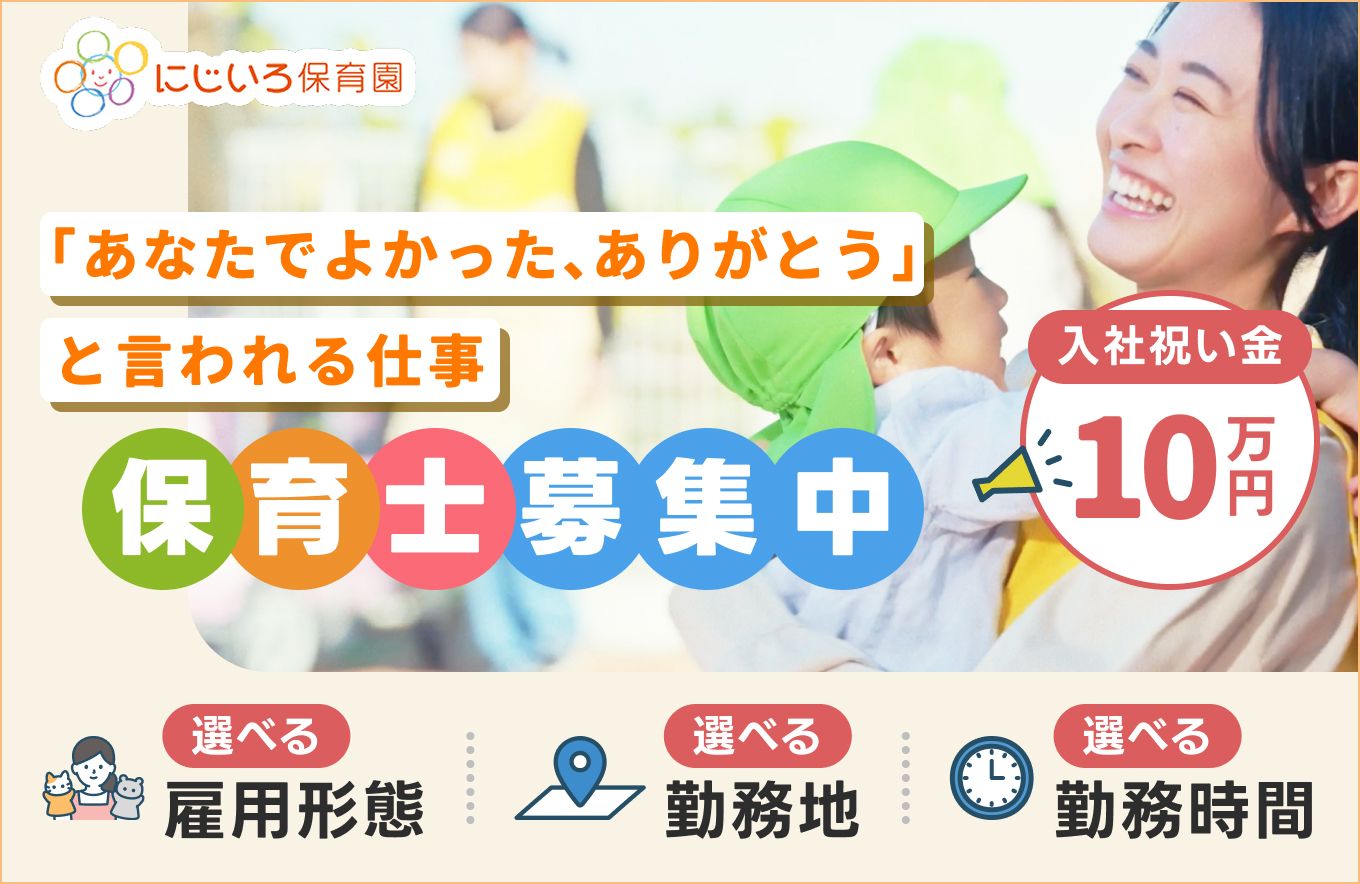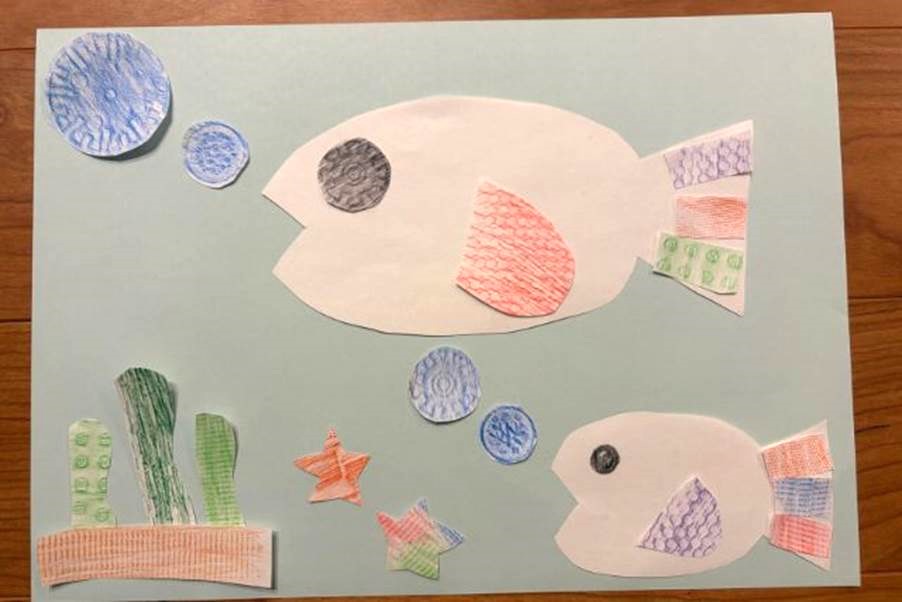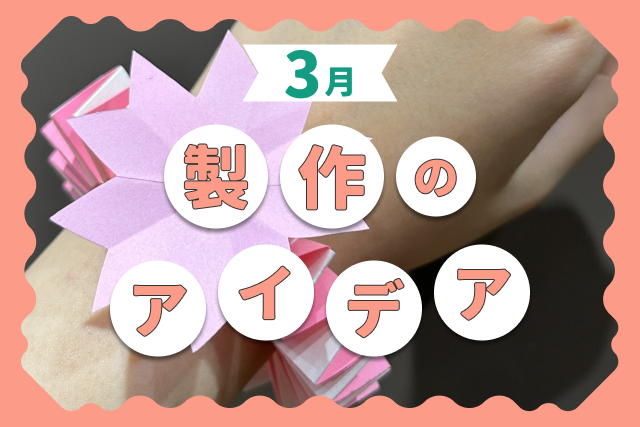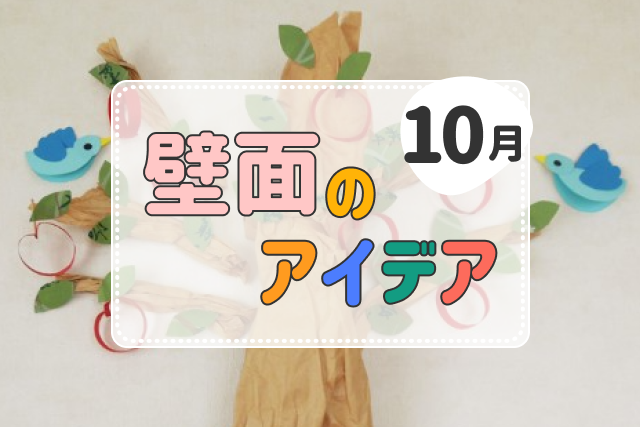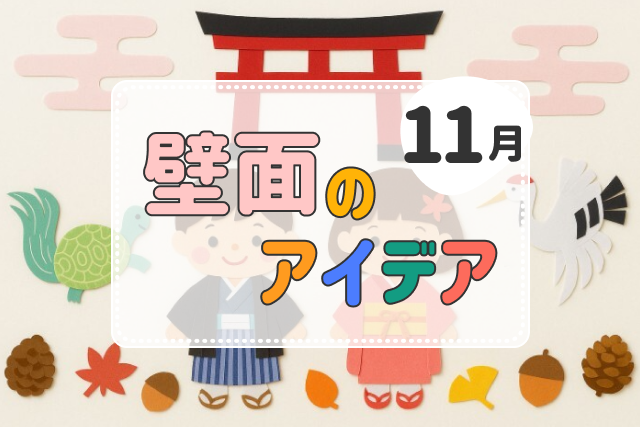2025.09.17
【例文あり】保育実習の目標|書き方のポイントをわかりやすく解説
保育実習に向けて、最初に取り組むべきなのが「目標を立てること」です。ただ、何を書けばよいのか迷う学生も少なくありませんこの記事では、目標を立てる意味や考え方、書き方のポイントを整理し、実習の段階に応じた具体的な例文を紹介します。
「保育実習の目標」を立てる意味とは?

保育実習の目標は、学びたいことや挑戦したいことを整理し、実習を有意義にするための出発点です。目標がなければ活動を漫然とこなしてしまい、振り返りや評価にもつながりにくくなります。具体的な目標を持つことで、実習中の行動に指針ができ、学びの視点も明確になります。また、実習終了後に達成度を確認することで次の課題を見つけやすくなります。
「保育実習の目標」考え方のポイント

保育実習の目標を立てるときは、自分を分析し、段階的に考えることが大切です。ここでは、目標を検討する際に押さえておきたい基本的な視点を紹介します。
自己分析
実習の目標を立てる前に、自分の得意なことや苦手なことを振り返ります。例えば「子どもと遊ぶのは得意だが、保護者への対応は経験が少ない」「絵本の読み聞かせは好きだが、集団をまとめるのは不安がある」といったように具体的に書き出すと整理しやすくなります。これまでの授業やボランティア経験から感じた課題をもとにすると、実習で重点的に学ぶべきテーマが見えてきます。
段階に合わせた目標設定
初めての実習、中期の実習、最終実習では求められる役割が異なります。初回は「園の雰囲気や子どもの生活を理解する」、中期は「援助や指導に積極的に関わる」、最終は「保育士としての一連の流れを自分で行う」といったように、段階ごとに目標を変えて設定します。
大目標と小目標を組み合わせる
「保育士として子どもとの関わりを深めたい」といった大きな方向性を決め、それを軸に、「一日一回は子どもに声をかける」など具体的な小目標を立てます。大目標で方向を示し、小目標で具体的な行動に落とし込むと整理しやすくなります。
指導者からの期待を踏まえる
実習要項や事前の説明会では、園や大学の指導者から具体的な到達目標が示されることがあります。それらを確認し、自分の目標に反映させると、実習で求められる姿勢に沿った計画になります。
「保育実習の目標」書き方のポイント

目標は思いつきで書くのではなく、明確な基準をもとに整理することが必要です。ここでは、実習の目標を書く際に押さえておきたい基本的な4つのポイントを紹介します。
▼「子どもとたくさん遊ぶ」と書く場合
-
SMARTの法則を活用する
「具体的(Specific)」「測定可能(Measurable)」「達成可能(Achievable)」「関連性(Relevant)」「期限(Time-bound)」の5つの視点に沿って目標を考えます。「毎日3人以上の園児に声をかける」とすると、実行しやすく振り返りもしやすくなります。 -
曖昧な表現は避ける
「積極的に」「しっかりと」といった表現は避け、行動の内容をはっきり書きます。例えば「積極的に子どもと遊ぶ」ではなく「自由遊びの時間に、子どもが好む遊具や取り組み方を観察し、必要に応じて声かけを行う」とすると、何をするかが明確になります。 -
教育者の視点を意識する
保育実習では、学生も教育者の一員として子どもに関わります。目標を書くときは、自分が学ぶ立場だけでなく、子どもの成長や安全に責任を持つ視点を盛り込みます。例えば「遊びの中で安全に配慮しながら、子どもの発達段階に合わせた援助を行う」といった表現にすると、教育者としての役割を意識した目標になります。 - 実習記録と結びつける
実習では、子どもの様子や自分の援助を実習日誌などに記録します。目標も、そこで記録する内容と関連づけて具体的に書くと整理しやすくなります。
例えば実習日誌に自由遊びの様子を書いたとしたら、その次の目標として「自由遊びの場面で子ども同士の会話を観察し、関わり方の特徴を理解する」と書くことができます。また製作遊びについて記録したのであれば、目標は「折り紙や絵を通して子どもの表現の仕方を観察し、年齢ごとの違いを理解する」とすると、行動がはっきりします。
「保育実習の目標」役立つ例文集と活用のヒント

ここでは、実習の段階ごとに基本的な目標例を紹介します。初回から最終までの流れを意識すると、自分に必要な学びが整理しやすくなります。
初期実習
園の雰囲気や子どもの生活を知ることが中心となるため、観察や理解に重点を置いた目標を立てます。
【例文】
- 子どもの一日の生活の流れを理解し、活動に合わせた援助を学ぶ。
- 園での安全面に注意しながら、子どもの様子を観察して記録する。
- 子どもとの関わりを通じて、年齢ごとの発達の違いを理解する。
- 保育者の声かけや援助の方法を観察し、自分なりに記録する。
- 実習記録を毎日整理し、学んだことを具体的に振り返る。
中期実習
実習に慣れてきた段階では、援助や部分的な指導に関わる目標を設定します。
【例文】
- 食事や着替えの場面で、子どもの自立を促す援助を行う。
- 絵本の読み聞かせを通じて、子どもが興味を持てる関わり方を実践する。
- 遊びの時間に子ども同士の関わりを観察し、トラブルや困っている様子があれば声をかけて調整する。
- 保育者の動きを観察し、掃除や準備など補助的な仕事を自分で判断して行う。
- 指導者の助言を受けながら、10分程度の活動を計画し子どもと実践する。
最終実習
保育士としての一連の流れを自分で担うことを意識し、主体的な実践を含む目標を書きます。
【例文】
- 一日の保育計画を自分で立て、指導者の助言を受けながら実践する。
- 複数の子どもと関わる中で、それぞれの発達段階に応じた援助を行う。
- 運動会や発表会などの行事の一部を担当し、責任を持って進行する。
- 保護者の送迎時に挨拶や簡単な声かけを自ら行い、適切な言葉遣いや立ち振る舞いを実践する。
- 実習後に自己評価を行い、できたこと・できなかったことを具体的に記録する。
各段階で共通して活用できる目標例
実習の段階を問わず、学生が意識して取り組みやすい目標もあります。
【例文】
- 子どもの安全を第一に考え、危険がないか常に確認する。
- 保育者の援助の方法を観察し、自分の言葉で記録する。
- 実習日誌をその日のうちに書き上げ、振り返りを残す。
- 子どもの小さな変化に気づき、指導者に報告する。
- 自分の言葉遣いや態度を意識し、保育士としてふさわしい姿勢を心がける。
例文活用のヒント
例文は参考資料として取り入れ、自分の課題や体験に合わせて具体的に書き換えましょう。
例えば「子どもの様子を観察する」という例文を活用する場合は、「午睡の時間に子どもの寝つき方を観察する」「戸外遊びで子どもが友達と関わる様子を観察する」といったように、実習中に注目したい場面を明記します。
また、「援助する」と書かれている例文なら、「着替えの場面でボタンのかけ外しを手伝う」「給食の配膳で子どもが自分でできるよう声をかける」と具体的にすると、行動が明確になります。
このように、例文をそのまま写すのではなく、実習内容に即した形に置き換えることで、自分に合った目標として活用できます。
「保育実習の目標」を立てた後に大切なこと
目標は立てて終わりではなく、実習の中で意識し続けることが大切です。日誌や記録にその日の達成度を書き込む、反省会で自分の行動を照らし合わせるといった工夫をすると、目標が実習に根づきます。達成できなかった部分も含めて確認することで、次に取り組むべき課題が見えやすくなります。
まとめ
保育実習の目標は、学びを明確にし、実習を有意義にするために欠かせません。立てた目標は振り返りの基準となり、自分の成長や今後の課題を整理する手がかりになります。また、実習で得た経験や気づきは、就職活動の自己PRや面接で具体的なエピソードとして語ることができ、将来にもつながります。実習を前向きに活かすためにも、事前に目標を定めて臨みましょう。
保育実習を通して、多くの経験ができます。ライクキッズが首都圏を中心に150園以上運営している「にじいろ保育園」では、保育実習を受け付けています。保育実習を通して、たくさんの大切なことを学んでみましょう!